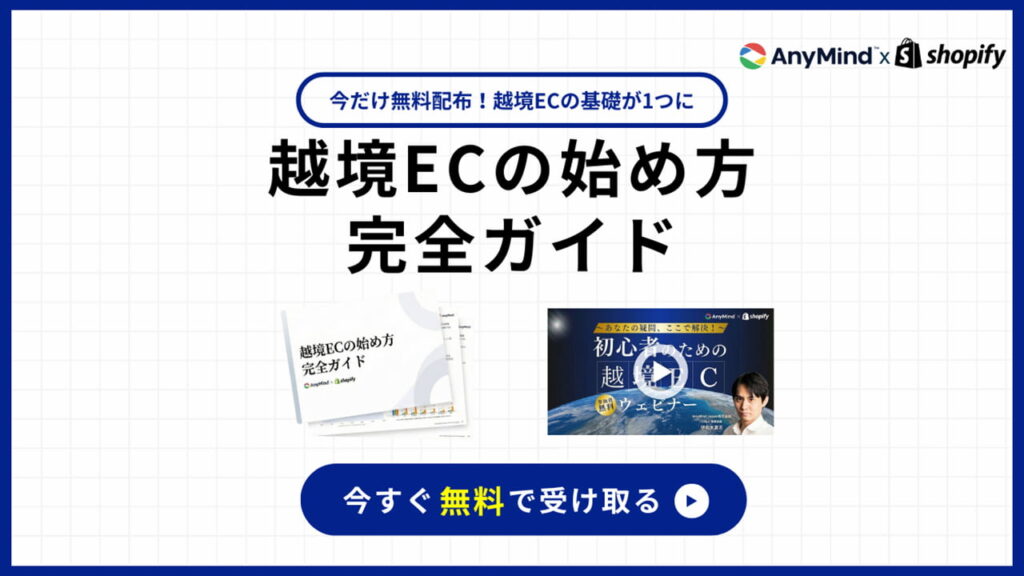東日本大震災の教訓を活かした作品も
—ほかに国内の事例で印象に残ったものはありますか。原野:
ナイキとはトーンが全然違いますが、滋賀県のプロモーション動画「ニュートンに学ぶ、これからの滋賀ノーマル」ですね。
ニュートンに学ぶ、これからの滋賀ノーマル_長尺ver
すごくふざけているけれど、ステイホームが実は“創造や発見のチャンス”であるというメッセージは非常に洞察に富んでいます。「みんながんばろう」というだけの広告が多い中、賢さが際立った広告でした。「お見合いする近江米・押し合いする近江米・お見舞いする近江米」と三段重ねで畳みかけるクライマックスは圧巻ですよ。