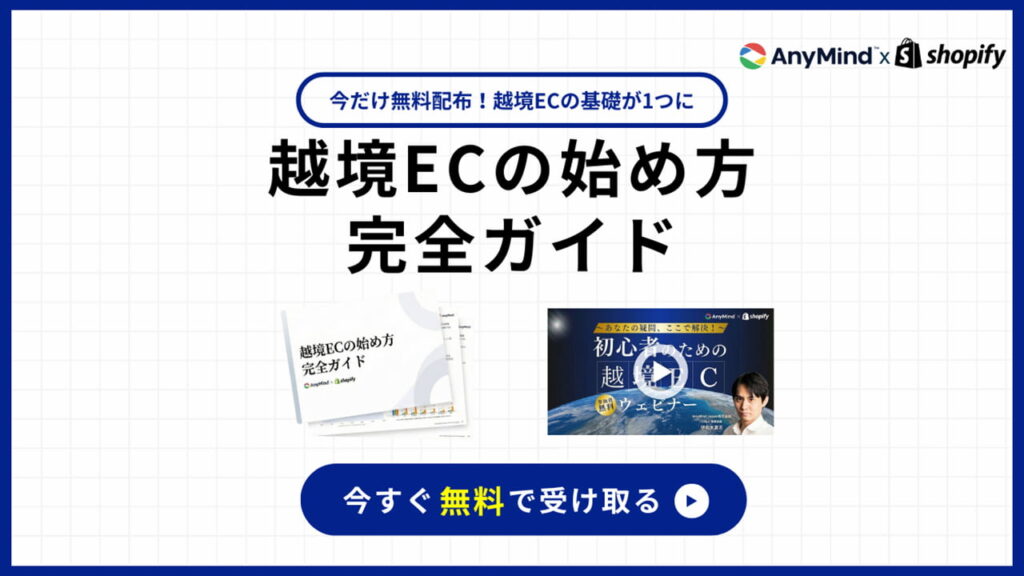ハッタリこそが成長につながった
——柿本さんは若手の頃、どのようなことを意識して過ごしていましたか?
若い頃は、人の真似ばかりしていましたね。最初に監督をやった時も、何をやればいいかわからず、これまで助手としてついてきた監督の真似をしていました。
ある時、恩師と仰いでいたオクナックの井之上伸也プロデューサーに作品を見せに行ったことがあります。10本ほどの作品が、軒並み落第点を食らったのですが、一個だけ「これは80点」と言われた作品があった。それが、初めて自分が必死にカメラを回した作品だったんです。
井之上さんは、こんなことを言いました。「カメラマンと“喧嘩”してないでしょ?ちゃんと戦ってる? 20代なんだから、望遠レンズなんか使わずに、ワイドでアーティストの顔に寄ったほうがいい」、と。
これまでたくさん人の真似をしてきたものの、そのどれもが自分らしくなかった。でも、たった一本褒められた作品だけは、誰かの真似じゃなかったんです。映像や写真には自分のマインドがちゃんと映り込むんだな、と身にしみてわかりました。そこからは、「自分らしさとは何か」を考えるフェーズに入っていったんです。
——若手時代を振り返って「成長につながった」と感じることは何ですか?
それは「ハッタリ」をきかせることですね。やったことがなくても「これ、できますか?」と聞かれたら「できますよ」と言っちゃう。例えば、CDジャケットとミュージックビデオを同じ世界観でつくりたい、と言われたことがあって。経験はなかったけど「写真と映像なんて一緒だろ」と思って引き受けたら、全然違った(笑)。その時にヤバいな、ちゃんと勉強しなきゃマズイことになるぞ、と思いました。
そこからは、師匠に教えを乞うたり、専門学校時代はロクに読まなかった教科書に初めて向き合った。ハッタリをきかせた以上、「やらざるを得ない状況」に追い込まれたんですね。
新しい依頼が来た時に「やったことがないから、できません」と言ったら、道はそこで終わってしまいます。つまり、ハッタリこそがその後の成長につながっていった、というわけです。
——若手時代の一番のライバルは誰でしたか?また、ライバルに勝つためにしていたことを教えて下さい。
ぼくが業界に入った頃は、フィルム全盛期でしたが、やがて、デジタル編集へ大きく変わるポイントを迎えます。時代は、従来のやり方にこだわる旧世代と、デジタルの無限の可能性に気づいた新世代とがクロスオーバーしていたわけです。