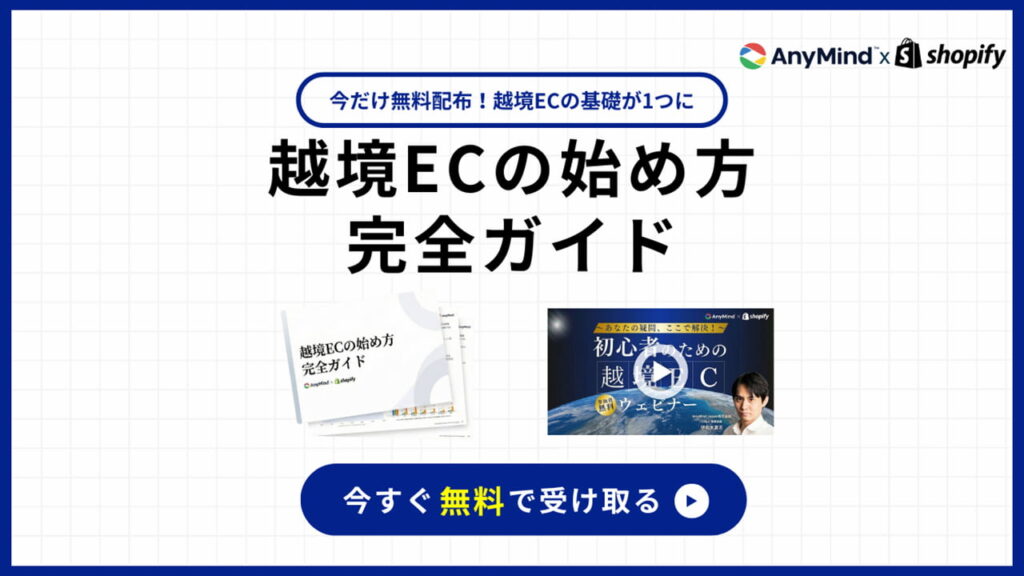特にSNSが浸透した環境ではトラブルが発生した際、実写化にかかわるメディア企業の制作者や編集者が誹謗中傷を受けるケースも少なくない。原作者の権利を守り、トラブルを避けるためにメディア企業に所属する編集者や制作者は、どんなことに配慮すればよいのでしょうか。
法律という視点から、実写化・ライツビジネスを巡る課題や今後の展開について考えることで、課題解決への糸口、あるいは作品の魅力の最大化を的確に行うことができるのではないか。そんな観点から、著作権法に詳しい骨董通り法律事務所の弁護士である、岡本健太郎氏に話を聞きました。
※本記事前篇は、こちらから
※本記事は情報、メディア、コミュニケーション、ジャーナリズムについて学びたい人たちのために、おもに学部レベルの教育を2年間にわたって行う教育組織である、東京大学大学院情報学環教育部の有志と『宣伝会議』編集部が連携して実施する「宣伝会議学生記者」企画によって制作されたものです。企画・取材・執筆をすべて教育部の学生が自ら行っています。
※本記事の企画・取材・執筆は教育部所属・永留琴子が担当しました。
――権利侵害や表現に関する問題はそれぞれのケースによって異なる曖昧さがあると推測するのですが、岡本先生はどのように向き合っているのでしょうか。また、私たちが気を付けるべきポイントがあれば教えてください。
過去の事例などに照らし、権利侵害になる場合とそうでない場合を判断できることも少なくありません。しかし、特に関係者間のトラブルについては、作品自体を検討するだけでなく、制作に携わる方々のコミュニケーションなど、関係者のやり取りも重視しています。制作意図をお聞きすることによって、作品の違った側面が見えてくることもあります。結局は、人それぞれの思いや考え方に向き合うことが大切だと思います。
また、「もしかしたら自分が間違っているかもしれない」といった疑いの意識も重要に思います。関係者がそうした意識を持つことのほか、予防の枠組み作りも重要だと思います。具体的には、契約書が、この枠組みのひとつです。契約書を作成しておくと、双方の立場が明確になり得るほか、トラブルが生じた際にも、契約といった根拠に基づく主張がしやすくなります。
――枠組みづくりが大切なのですね。中でも作品の実写化において、トラブルを回避する上で心がけるべきことはありますか。
例えば、漫画を映像化する場合を想定すると、出版社が原作者から作品を預かり、原作者に代わって、テレビ局側とやり取りをすることが多いように思います。改変や演出に関するトラブルの回避を想定すると、こうしたやり取りに際しては、出版社側としては、原作者が変更したくない部分、避けてほしいことなどがあれば、原作者の意向を把握し、制作者側に伝えておくことが大切です。
しかし、制作者側に、その意向が上手く伝わらず、映像作品に反映されないこともあるように思います。契約書も立場や考え方を明確化する手段ですが、そのほか、出版社側の視点では、必要に応じて、原作者本人との面談や原作者のメモを渡すなど、原作者が制作者側と直接コミュニケーションを取ることも有益かもしれません。
折しも、先日、日本テレビと小学館から、それぞれ報告書が公表されていましたね。それぞれの主張にすれ違いがありましたが、制作者と出版社の立場が示されているように思いました。契約書が締結され、また、文書での連絡や直接のコミュニケーションがより多ければ、現場の対応も変わっていたのかもしれません。また、部外者の「たられば」で恐縮ですが、契約書が締結されていれば、その条項次第では、関係者によるSNSの利用も制限できた可能性も感じています。