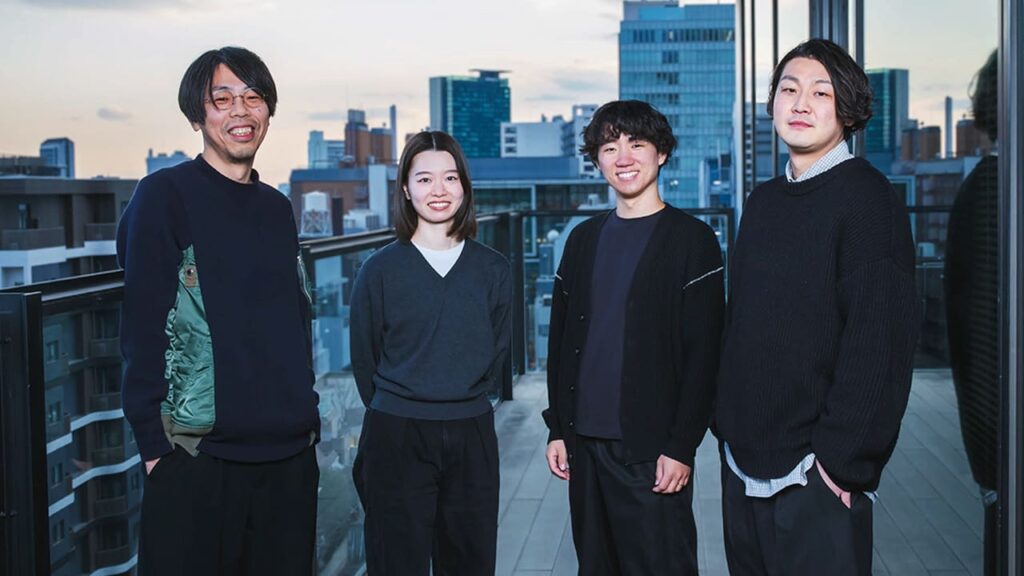11月28日に大阪で開催された「宣伝会議サミット/環境ビジネス・カンファレンス in Osaka」で、生成AIのビジネス実装をテーマにした2つのセッションが行われた。 最初に、対面販売にこだわり続けてきた化粧品メーカー・アルビオンの榊原隆之氏と、MMOL Holdings(ミリモルホールディングス)の河野貴伸氏が登壇。EC未経験の組織がいかにしてチャットボットや生成AIを導入し、顧客体験(CX)を向上させたか、その変革の裏側にある「ブランドの言語化」の重要性を語った。
続いては、アマナの谷野弘知氏と野口貴裕氏が登壇し、進化する生成AIを取り巻く著作権リスクや炎上リスクを法的な観点から解説するとともに、クリエイティブ制作における効果的なAI活用法を提示した。
「接客」を核としたECへの挑戦と現場の反発
創業以来70年近く「対面販売」を重視し、EC販売を手がけてこなかったアルビオン。本講演では、同社で「アナスイ」「ポール&ジョー」の国内販売責任者を務める榊原氏が、EC立ち上げとAI導入の経緯を語った。 榊原氏は「ECを否定しているわけではなく、店頭での接客体験のオンラインでの再現が難しかった」とし、ECを開始する条件として「接客を核にすること」を掲げた。そこで導入したのがチャットツールである。
しかし、導入当初は元美容部員であるEC担当スタッフから猛反発を受けた。「チャットなんて誰も使いません」「メールと電話で十分です」と突き放された榊原氏は、自らチャット対応を開始。すると、従来のメール対応が「商品不備や配送」などの事後対応中心だったのに対し、チャットでは「使用感はどう?」「私に似合う色は?」といった購入前の相談が圧倒的に増えた。これによりスタッフの意識も変わり、チャットが顧客との重要な接点として定着していった。
生成AI導入による「サイレントカスタマー」の掘り起こし
次なる課題は、スタッフが不在となる夜間や土日の対応だった。榊原氏がAIチャットボットの導入を提案すると、再び現場からは「私たちの接客をAIにやらせるのか」と強い反発が起きた。それでも「お客様が最もリラックスしている夜間に即答できる環境が必要だ」と説得し導入を断行した結果、問い合わせ数は劇的に増加した。
• コミュニケーション量の増大: 有人対応のみの時と比較し、AI導入後は圧倒的な数の相談が寄せられるようになった。これは「人に聞くほどではないが、AIなら気軽に聞ける」という潜在的なニーズ(サイレントカスタマー)を掘り起こした結果である。
• CVRの向上: AIが一次対応を行い、より深い相談を有人へつなぐハイブリッド体制を構築したことで、コミュニケーション総量が増え、結果としてコンバージョン率(CVR)も向上した。
• 多言語対応: インバウンド需要による店頭の混雑(オーバーツーリズム)に対し、多言語対応可能なAIが事前相談を受けることで、店頭オペレーションの負荷軽減にも寄与している。
榊原氏は「AIは効率化のためではなく、新しい価値(24時間対応や気軽な相談)を作るために導入した」と強調し、AIに数を任せることで、人間はより「パーソナルな対応」や「開封体験(Unboxing)の演出」といった高付加価値な業務に注力できるようになったと語った。
AI活用の成功鍵は「ブランドの言語化」
MMOL Holdingsの河野氏は、アルビオンの事例を「ブランドの羅針盤(Compass)が機能した好例」と分析した。 多くの企業でAI活用が進まない真因は、技術不足ではなく「言語化の欠落」にある。AIは行間を読めないため、「新商品の提案書を作って」という抽象的な指示では精度が出ない。「誰に向けた、どんな価値を持つブランドなのか」という前提条件(コンテキスト)を明確に入力する必要がある。
アルビオンの場合、長年培ってきた「接客マニュアル」や「ブランドの公式サイト」自体が、AIにとっての良質な「教科書(入力データ)」となった。河野氏は、AI時代だからこそ、企業のPurposeやVision、NG表現などを構造化して言語化し、AIが理解できるようにブランドの情報を設計する概念「Brand OS)で管理することが重要であると提言した。 また、リスク管理(ガバナンス)についても、「AIを使わせない」のではなく、AIがハルシネーション(誤回答)を起こした際のエスカレーションフローを事前に設計し、人間が承認プロセスに関与する「HITL(Human-in-the-Loop)」の体制を構築することが、ブランドを守りながら進化させる鍵であると結んだ。
加速する生成AIの普及と法的リスクの現状
本セッションでは、クリエイティブとテクノロジーを融合させるアマナが、生成AIの法的課題と活用法について解説した。ChatGPTがわずか2カ月でユーザー数1億人を突破するなど普及が加速する中、企業は「法的リスク」と「炎上リスク」の双方を理解する必要がある。
法務担当の野口氏は、日本の著作権法におけるAIの取り扱いを以下の3点で解説した。
1. 学習段階(Input): 日本は著作権法第30条の4により、情報解析(学習)目的であれば、原則として著作物の利用が認められている。ただし、権利者の利益を不当に害する場合は例外となる。また、意図的に学習データに含まれる著作物の創作的表現をそのまま出力させることを目的とした追加学習などは、30条の4の適用外。
2. 生成段階(Output): AIが自律的に生成したものには原則として著作物にはならない。ただし、人間が道具として使い、創作的寄与(プロンプトの工夫や加筆修正など)があれば著作物として認められる可能性がある。
3. 侵害判断(Similarity & Reliance): AI生成物が既存の著作物に似てしまった場合、著作権侵害となるには「類似性(似ているか)」と「依拠性(既存作品を知っていて参考にしたか)」の両方が必要となる。特定の作品名や作家名をプロンプトに入力した場合(例:「ドラえもん風」)や、i2i(画像から画像を生成)を行った場合は、依拠性が認められやすいため、既存の著作物と類似した生成物が出力されると著作権侵害リスクが高まる。
法的にはセーフでも「炎上」するレピュテーションリスク
野口氏は、法的リスク以上に日本で頻発しているのが「クレーム・炎上リスク」であると指摘した。
• 事例1 海上保安庁のポスター: イラストレーターを使わずAIで作成したと見られるポスターに対し、「絵としての整合性がおかしい」「クリエイターの仕事を奪うのか」といった批判が殺到し、掲示取りやめに追い込まれた。
• 事例2 Google GeminiのCM: 父親が娘のファンレターをAIに書かせようとする内容が大炎上。「子供の創造性を奪う」と批判され放送中止となった。
• 事例3 ジブリ風画像: 有名CEOがSNSアイコンにしたことで話題となったが、法的には「作風・画風」の模倣は著作権侵害にあたらないとされているものの、一部の層から反発を招いた。
これらの事例から、法律を守っていれば良いというわけではなく、AI生成物に対する大衆の感情(不気味の谷現象や、手抜き感への嫌悪、倫理的な問題など)を考慮したリスクマネジメントが不可欠であることが示された。
クリエイティブにおける効果的な活用とガイドライン
プロデューサーの谷野氏は、リスクを踏まえた上での効果的なAI活用事例を紹介した。
• パッケージデザインの合意形成: 従来、デザイナーが手書きで数案出し、修正を繰り返していたフローを刷新。商談の場でAIを使ってリアルタイムにイメージを出力し、方向性を固めてからイラストレーターに発注することで、手戻りを大幅に削減した。
• グローバルブランドの統一: 国ごとにバラバラになりがちなビジュアルトーンを統一するため、ブランドの世界観を定義する「プロンプト(呪文)」を開発し、納品。
• プロのテクニック: AIでフォトリアルな画像を生成する際、プロンプトに「カメラのレンズ設定」や「被写界深度」などの撮影用語を加えるだけで、品質が劇的に向上するという実践的なテクニックも披露された。
最後に両氏は、企業がAIを活用するためには、一律禁止にするのではなく、自社の商材やリスク許容度に合わせた「独自ガイドライン」を策定することが、AIを味方につける第一歩であると締めくくった。
お問い合わせ
株式会社アマナ
住所:〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-3-7 VORT御堂筋本町
TEL:06-6227-1515
Mail:k.tanino@amana.jp