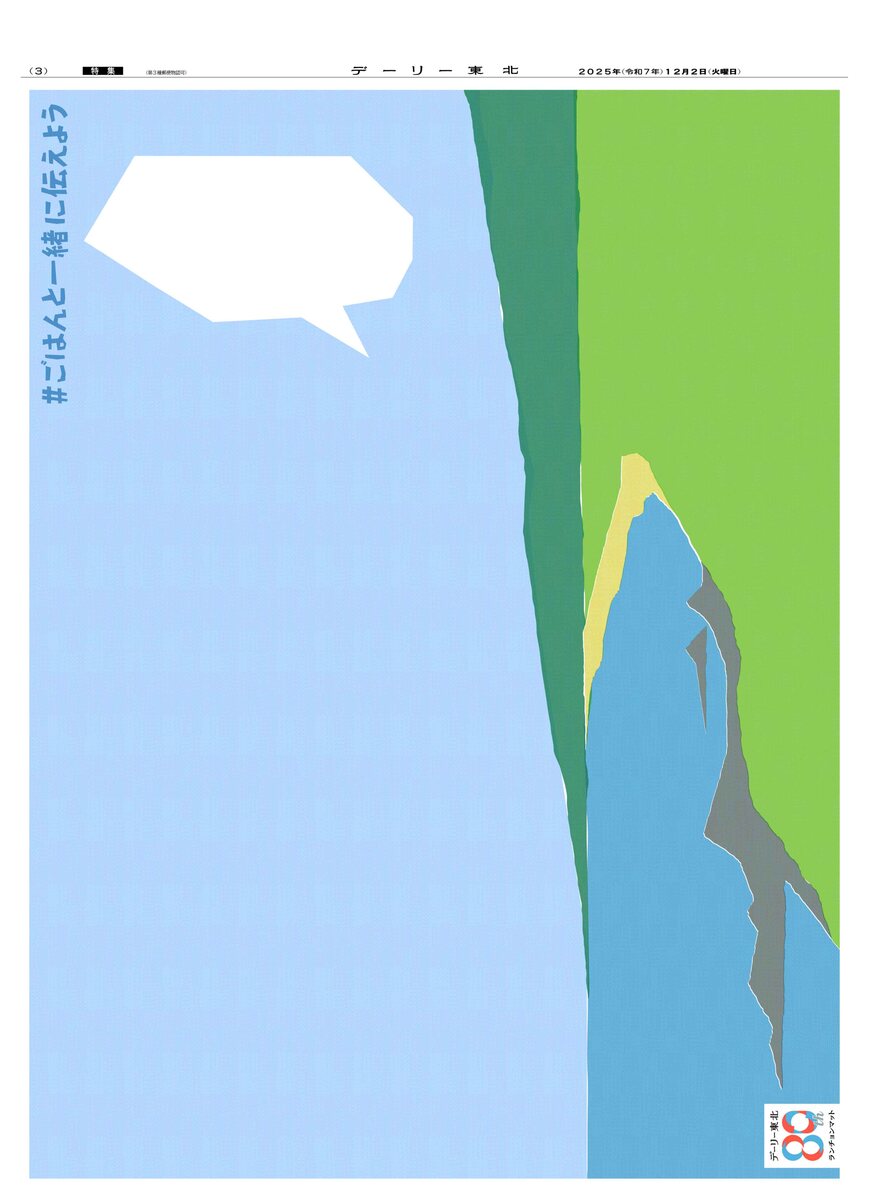「情報は増えたが、地域で同じ話題を共有する場は減っている」――。そんな地方紙が直面する課題に対し、青森県八戸市に拠点を置くデーリー東北新聞社は、創刊80周年企画として「北奥羽の食」をテーマにしたプロジェクトを展開した。
新聞を単なる情報媒体から、食卓での「会話を生むツール」へ。同社地域ビジネス局ソリューション営業部の三浦慶太氏に、今回のプロジェクトの戦略的背景を聞いた。
新聞の「30段サイズ」は、食卓のサイズと同じ
今回の企画の核となったのは、2025年12月2日付の別刷り特集号だ。
同社は「ニュースは全国どこでも見られる今、地方紙は地域の暮らしに直結する話を、読まれる理由をつくって届ける必要がある」という危機感を抱いていたという。そこで着目したのが、新聞の物理的な特性。実は新聞を広げると、日本の一般的なダイニングテーブルの長辺とほぼ一致するサイズになるのだ。
「新聞は物理的に紙が大きい。この大きさはスマホにはない強みです。大きいからこそ、食卓で広げて、向かい合って同じ面を見ながら話せる可能性があると考えました」と三浦氏は語る。
この特性を活かし、紙面を「2人用ランチョンマット」としてデザインした。青森県八戸市の海岸「種差海岸」を彩る花「ハマナス」をあしらい、自宅で使いたくなるクリエイティブを追求した。紙面には地域の食にまつわるトリビアや、感謝を伝える吹き出しを配置。このほかにもすごろくや飲食店へのポスター配布企画など、「情報を届ける」だけでなく、「読んだ後に話が始まる」体験設計をちりばめた。
表紙と裏表紙を連動させ、「ハマナス」をあしらった。
中面にはすごろくや、メッセージを書き込める一人分のランチョンマット、学校給食の振り返り特集など、さまざまな切り口で「食」と向き合う企画が展開されている。
「紙面の中」で終わらせない展開
配布された新聞は、家庭だけでなく八戸市内の飲食店でも実際に活用された。新聞社自らが足を運び、各店500枚ずつのランチョンマットを提供。店舗というリアルな接点で「新聞が使われ、会話が生まれるシーン」を創出した。あわせて制作した飲食店応援ポスターの申し込みも、現在までに約50店舗に達したという。
また、読者参加型企画として実施した「復-1グランプリ」では、もう一度食べたい、閉店した名店の味を募集。二次投票では1000件を超える投票があった。