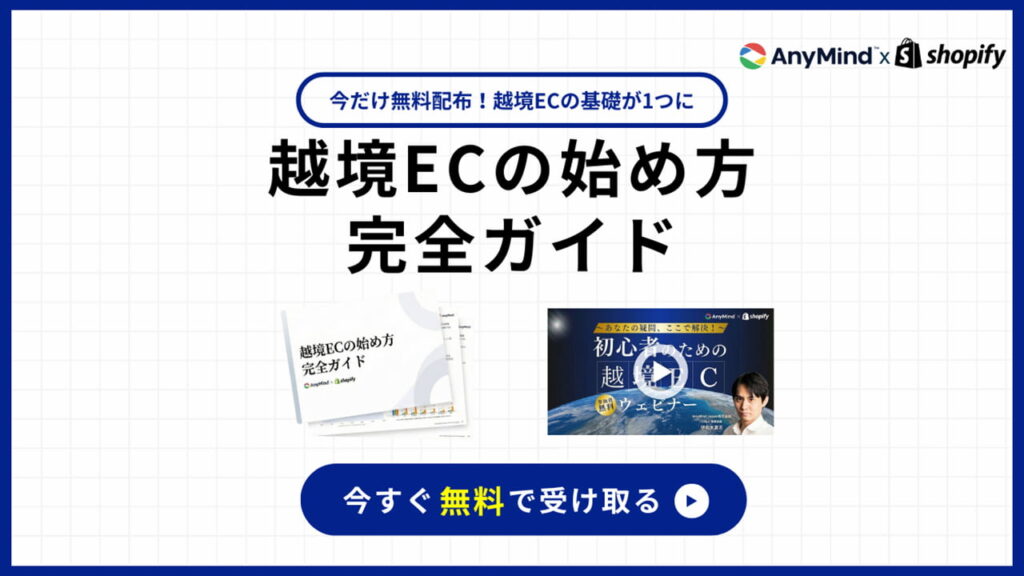2022年、読売ジャイアンツは本拠地である東京ドームの大幅なリニューアルと同時にブランドムービーを刷新した。多くのファンを魅了したその映像演出の手法について、読売新聞東京本社事業局野球事業部の森菜々穂氏と、ソニー・ミュージックソリューションズの代田兼一郎氏に話を伺った。
映像のつくり手として意識する情熱とフィロソフィー
——自己紹介および「映像」にまつわるご自身のエピソードを聞かせてください。
森
:読売新聞東京本社事業局野球事業部の森です。私の主な仕事は、東京ドームでの巨人戦での場内演出です。実は私、小さいころは映像よりも活字派だったので、映画やアニメはほとんど見ていませんでした。両親によると、好きなテレビ番組は天気予報だったらしいんですが(笑)、それぐらい、当時は本を読んで過ごしていましたね。
代田
:ソニー・ミュージックソリューションズでクリエイティブディレクターをしている、代田です。ジャイアンツをはじめとするスポーツチームや、アーティストなどに関わるコミュニケーションデザイン、メタバースプラットフォームの体験デザインまで、幅広い領域を担当しています。
映像を「つくる側」の目線で言うと、僕はコンセプトメーカーなのでクライアントの根底に流れているフィロソフィーに徹底的に目を向けるようにしています。「このブランドはどうあるべきなのか?どうありたいのか?」を深掘りしながら、観る人に深く刺さる表現になることを目指しています。
「体験」全体をデザインする映像を
——映像や動画をインプットする際に、あえて意識していることはありますか?
森
:演出担当になってから一年半なのですが、映像やクリエイティブをいろいろとインプットするようになりました。特に、MLBなどの海外スポーツの演出映像をYouTubeで見るようにしています。街中のサイネージで流れるショートムービーなどからも、人の感情に訴えかけるアプローチを学ばせてもらっていますね。
特に、印象に残っているのは、2016-17年秋冬の「グッチ」のブランディングムービー。新宿の街並みに触発されたもので、パチンコ店やデコトラなど、ハイブランドには似つかわしくないイメージを取り入れながらも、むしろ高貴な感じすら伝わってきました。これはいい意味で裏切られた作品として、すごく印象に残っていますね。