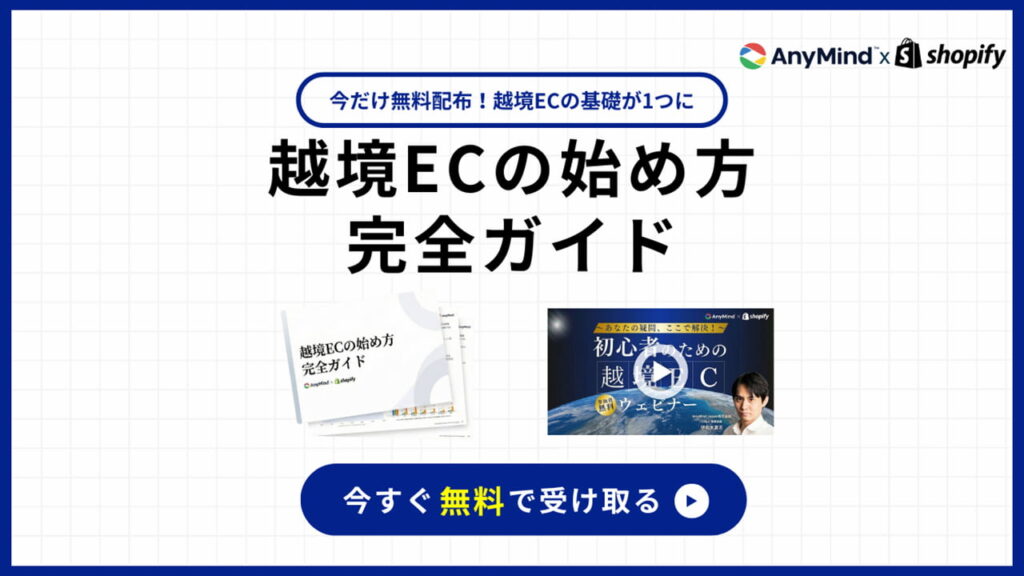日本パブリックリレーションズ協会(PRSJ)が主催する、企業・団体の広報部門やPR会社が実施するパブリックリレーションズの事例を対象とした「PRアワード」のエントリー受付の締め切りが10月15日に迫っている。本記事では、「PRアワード」審査委員長を務める田上智子氏(シナジア)と2023年からPR部門が独立した「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」(ACC賞)でPR部門審査委員長を務める眞野昌子氏(日本マクドナルド 広報部 部長※取材時)の対談を掲載。嶋浩一郎氏(博報堂/博報堂ケトル)をファシリテーターとしてまじえ、2つの賞の共通点や違い、PRパーソンに求められる「技」について議論する。
関連記事
社会を動かした受賞事例が示すPRの可能性
嶋:それぞれのアワードの審査方針をうかがってきて、では過去の受賞事例を見てみましょうか。実は去年2024年度は、グランプリが同じだったんですよね。マイナビの「座ってイイッスPROJECT」です。
これは小売店舗の店員さんが立ちっぱなしでいなければならないという慣習を覆していこうというキャンペーンです。就職・転職情報サイトを運営する会社が、レジスペースに置く椅子を実際につくって頒布したという非常に面白い事例でした。ACC賞、PRアワードではそれぞれどんな議論がされたのでしょうか。
眞野:これは審査委員一同合意のもとグランプリに決まりました。評価されたポイントは、短期間で多くのステークホルダーを巻き込んで、社会への実装までやり遂げたところでした。
また、このプロジェクトでは生活者にアンケートを取っており、「小売店で店員さんが座っていたらどう思いますか」を聞いて、「別に気にならない、いいんじゃないか」という生活者の声を紹介しています。ここで複眼的な視点が非常に活かされています。
嶋:先ほどのストーリーテリングの手法として、多様な立場の人たちの意見を吸い上げつつ、合意を図っていくプロセスがあるんですね。
僕が面白いなと思ったのは、マイナビのアルバイト募集サイトで「座ってできるバイト」コーナーを設けていた点です。「座ってできる」が新しいバイト選びの基準になることを示す良い取り組みだと思いました。田上さん、PRアワードではいかがでしたか。
田上:審査の観点はACC賞と共通する部分が多々ありますね。付け加えるなら、「立ちっぱなし問題」を通じて大きな社会課題に焦点を当てた取り組みであることも挙げられます。
日本では労働力の不足が加速し、シニアの労働環境も含めて、今後労働環境をより良いものにしていくかは、店員さんだけでなく社会全体の課題につながっています。そこに着眼して、眞野さんがおっしゃるように、キャンペーンだけでなく実際にプロダクトをつくるところまでやり遂げたのは、社会的な視点、戦略、実装まですべてつながる、非常にPR的な好事例でした。
そしてこの取り組みは、オーセンティシティという視点も非常によい形で満たしています。これは行政にも、雇用主にもできないキャンペーンで、たとえ巨大小売企業が始めたとしても、影響力は大きくはあるものの、一社だけで世の中の当たり前をつくっていくのは難しいことです。マイナビは雇う企業と雇われる労働者の間にいる企業だからこそ、真ん中の立ち位置を活用して社会全体に波及する動きをつくり出していったところが、非常にオーセンティシティが高いと感じました。
社会の新しい常識がパブリックリレーションズで生まれた瞬間を見た思いで、私もとても感動しましたね。
嶋:同じグランプリ事例でもACC賞、PRアワードではスポットライトの当てかたが異なる部分もあるんですね。ではこれはACC賞らしい、PRアワードらしいと思う事例も教えてください。
眞野:私は2023年度、ACC賞PR部門のグランプリだったヘラルボニーの「1・31 異彩の日 ヘラルボニー企業キャンペーン」が印象的でした。
嶋:ヘラルボニーは障害のあるアーティストによる意匠をIP化してさまざまなプロダクトをつくり、収益を上げるビジネスモデルを開発している会社です。それが霞ヶ関駅などで企業ポスター「鳥肌が立つ、確定申告がある。」を掲出したんですよね。障害のあるアーティストの親御さんの、我が子がこんなに収入を得ることができたのかという驚きとともに、確定申告の書類をポスターにしたという。
眞野:国税局のある霞ヶ関駅にポスターを貼るという、ごくシンプルなPR活動なのですが、目の付けどころとコピーが非常に秀逸で高く評価されました。
嶋:メッセージが強く伝わる企業PRですよね。PRはファクトが非常に大事で、ストーリーの中核にファクトを置くのがPRパーソンのスキルのひとつであると言えます。ヘラルボニーはたったひとり、n=1のファクトを見つけて、それが世の中を動かしていく最初のドミノになったというクリエイティブでした。
田上:障害者アートだから支援のために買うというのではなく、プロダクト自体が素敵だからほしくなるという、素敵なIPですよね。
私からPRアワードらしい事例として紹介したいのは、2019年度のグランプリとなった大阪府住宅供給公社の『茶山台団地再生プロジェクト』です。若者離れによる入居者の減少など課題が山積していた大阪・茶山台団地で、その衰退に歯止めをかけるべく、住民を「団地再生に共に取り組むパートナー」と捉え、独自の課題解決策を企画・実行しました。
ニュータウン団地の老朽化と高齢化、これは茶山台団地だけでなく日本中で社会問題になっています。それに対して、これまでできなかった大胆なリノベーションを施し、小さな住戸を2つつなげてゆったりとした90㎡の住戸にするなど、若い世代にも魅力的な住まいに変えていきました。
特に私が感心したのは、空室に住民が本を持ち寄って図書館をつくり、コミュニティスペースにした施策です。問題になっている空室率の高さをメリットに転じて、さらに住民と一緒にコミュニティを形成しました。ハード面とソフト面、双方の改善を住民と一緒に成し遂げていった共創から新しい価値を生み出していったところは、これぞパブリックリレーションズの本質だなという思いでした。審査委員一同、これはすごいと話したのが記憶に残っています。
嶋:団地の暮らし方の常識を変えていく、実際に場をつくっていくところが面白い仕事ですよね。
田上:2019年度は私がPRアワードの審査委員になって1年めでした。何十年もメーカーに勤めて、ものを売る、社会と向き合う仕事をしてきてパブリックリレーションズもわかっていたつもりになっていました。でもこの事例を見て、「パブリックリレーションズって本当に社会を変えていけるんだ!」と、可能性の大きさに衝撃を受けた事例でしたね。
嶋:そういうPRの可能性を、もっと世の中に示していきたいですよね。
企業と社会をつなぐPRの“技”とは
嶋:事例のお話を聞きながら、両アワードでは、これまで暗黙知だったり可視化されないままだったりしたPRの“技”に光が当てられていると思います。おふたりは、PRの技とはどのようなものだと捉えていますか。
田上:広報・PRの技は、事業体と社会を結びつける“橋”を架ける技術のことだと考えています。事業体と社会のちょうど境目に立ち、時代の流れとともに変わっていく社会を見据えながら、橋が架かりそうなポイントを見つけていくのも技だし、橋が架けられそうにないときには、社内外問わず仲間を見つけてポイントを探っていくのも技ですよね。
眞野:橋を架ける役割でもあり、窓を開く役割でもありますよね。会社の中にいるとどうしても中の論理で動いてしまってそれに気づかないこともあります。メディアや外部のステークホルダーに意見を聞いて、それをちゃんと会社の中にフィードバックして連結していくのもまた、広報・PRの技なんじゃないかと思います。
嶋:社会の中で自社の商品やサービスがどう役に立つのかを見極めて事業活動していくことは、「自社が何をできるのか」とは少し違う文脈で考えないといけないですよね。
田上:そうなんです。客観性と主体性を常に行き来することがPRの技のひとつかなと思います。それがベースの技。そしてその表出として「この手があったか!」というようなアイデアで突破していくのが、より上位の技というのでしょうか。
アワードの応募作を見ることは、そのアイデアの引き出しをたくさん持つことにつながりますよね。アワードの価値は自分の技を磨くところにもあると思います。
眞野:外と中をつなぐ接点としては、必ずしも攻めの広報だけでなく、守りの広報にも同じことが言えますよね。パブリックアフェアーズや危機管理の中でも、それぞれのステークホルダーの視点をよく理解することが必要です。そこにもPRの技、クリエイティビティは発揮されています。
田上:守れるという自信がない限り、攻めるための大胆な一歩は踏み出せないですよね。だから、私は守りが強いことは攻めにもつながると考えています。なかなか守りの部分は、表だってエントリーできない事情もあるので難しいのですが……。
嶋:パブリックアフェアーズなどの仕事も、アワードを受賞していますよね。そういう仕事も是非エントリーしてもらいたいですね。
メディアであれ生活者であれ、どんなステークホルダーに対しても、合意形成していくことがパブリックリレーションズの第一歩で。広告やマーケティングは「人との違い」を伝えていくのが得意分野ですが、PRの場合はさまざまな人との「同じ」を見つけていくのが技ですよね。
田上:まさにその通りですね。それぞれ異なる関心や利益を抱えた人たちと、重なる部分を小さくても見つけていくことがなにより大事です。意見が違って対立が生まれそうなところにも、必ず重なるところはある。諦めず根気よく向き合って握手をして、巻き込んでいく力が求められますね。