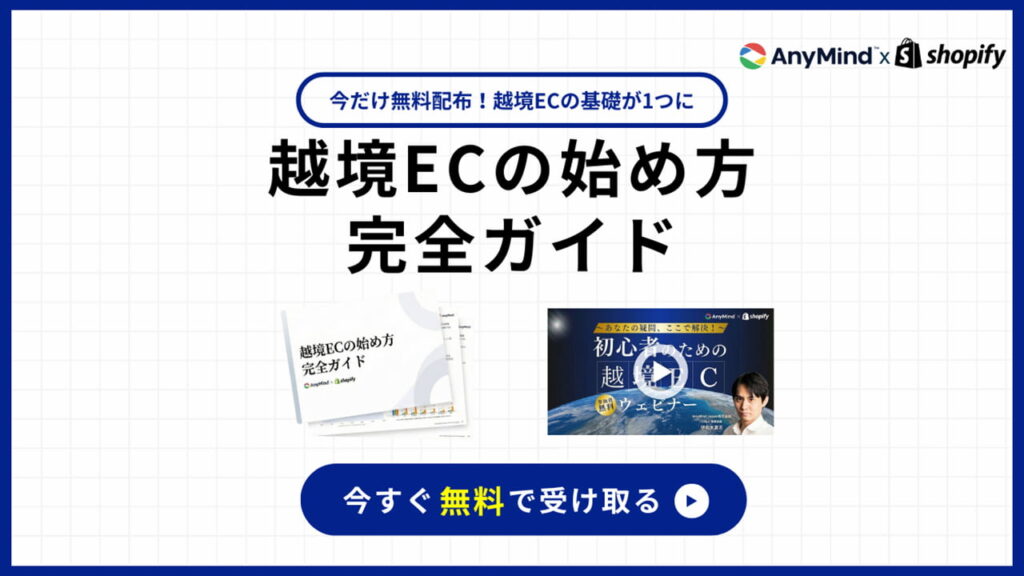頭で考えさせるものが奪われていき、身体で動かすものばかりになっていく
東:
ただ僕は、「役立つ広告」という概念に少し疑問があるとすれば、役立つコンテンツで一番強いのはポルノだと思うんです。その実用性に依存しているメディアはたくさんあって、多くの雑誌でグラビアが載っているように、それがリアリティとしてある。そうすると、何かのコンテンツプラットフォームが初期に拡大を目指そうとすれば、ポルノ的何かを活用すればいいということにもなりかねない。「使ってもらえる」というのは、それと似ているような気がするんですよね。