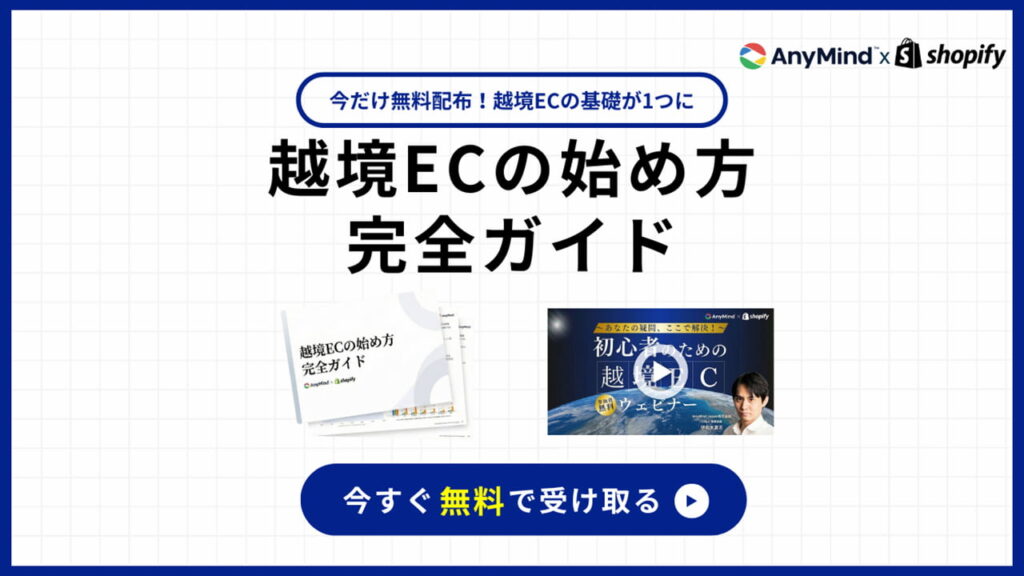はじめに
企業や役所などの広報業務は、記者とのつきあいなしでは成り立たない。
オウンドメディアやSNSなど、情報を直接発信できるツールが増えたことは事実だ。しかし、大手メディアの影響力は今も無視できない。ネットで「バズった(もしくは炎上した)」事例を見ても、規模が大きかったものはSNS単独で情報が拡散されているわけではない。ネットで話題になっていること自体をマスコミが「ニュース」として取り上げ、報道とクチコミの相乗効果によって爆発的な拡散が引き起こされているのが実態だ。
一方、記者の日常業務も、企業などの広報がいなければ成り立たない。ニュースの「ネタ元」のかなりの部分は、記者クラブに投げ込まれるプレスリリースだ。幹部などから話を聞く際も、夜討ち朝駆けなどのオフレコ取材を除けば広報にセッティングしてもらうことが多い。こうした広報への依存度の高さは「発表ジャーナリズム」として批判されるほどだ。
新聞記者だった筆者の経験から言っても、日本における記者と広報は、お互いが最も重要なビジネスパートナーだ。そして、企業などが組織のガバナンス(統治)を強化し、リスク管理の体制を整える中で、取材対応を広報経由に一本化する流れは年々強まってきた。記者の突撃取材に対する典型的な逃げ口上が「広報を通してください」であることは、それを象徴している。
しかし、こうした記者と広報の関係には変化の兆しもある。背景にあるのは、新聞やテレビといったオールドメディアの経営難だ。
顧客離れと広告のネットシフトが続く中、報道各社はこれまで聖域とされてきた記者や取材費の削減に手を付け始めた。日本の大手メディアが誇ってきた、世界に例を見ない規模の取材網は崩壊しつつあるのだ。これは広報の側からすれば、記者クラブにリリースを投げ込みさえすれば、報道機関が競うように報じてくれた時代の終わりが近づいていることを意味する。
一方、現場の人手不足を背景に、報道機関は業務の「選択と集中」を進めつつある。リリースの記事化などルーティンワークは通信社に任せ、より付加価値が高い「調査報道」に力を入れ始めたのだ。筆者の古巣である日本経済新聞も、調査報道の専門チームを立ち上げたり、データ分析の専門知識を持つ人材を採用したりして、体制の強化を進めている。