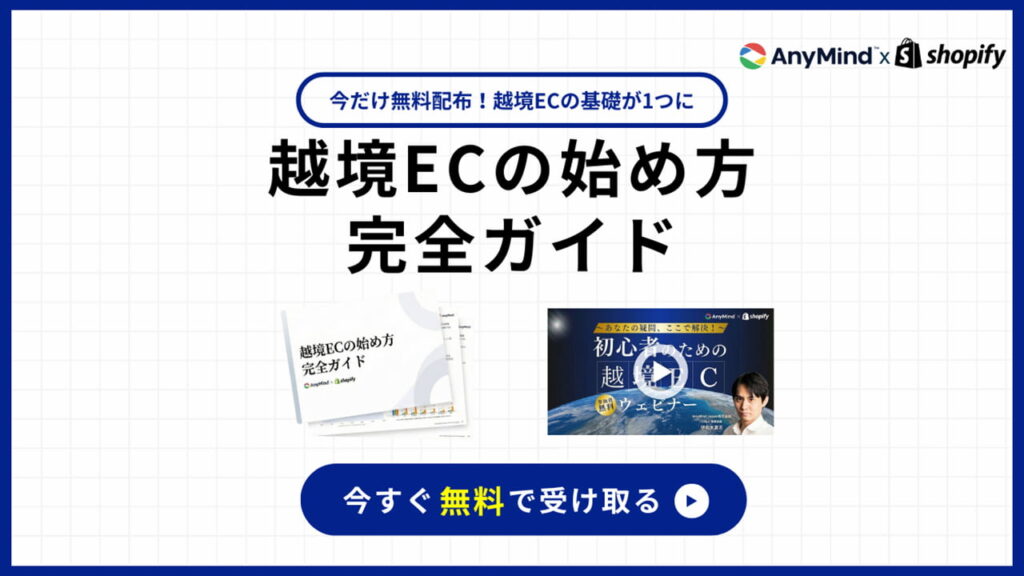そんな『コピー年鑑』をテーマに、本コラムではTCC会員であるコピーライターやプランナーが執筆。第1回目は、Netflix「人間まるだし。」などを手がけられた三島邦彦さんです。
コピーライターに何か資質があるとすれば、それは書く力ではなく読む力なのかもしれません。コピーから多くのものを受け取る人。たとえそれが勘違いだとしても、これは自分に向けたメッセージだと思ったり、これを超えるものを自分はいつか書くだろうと夢想したり、コピーを夢中で読みふけることができる人は、コピーライターに向いていると思います。
ある時ラジオで翻訳家の岸本佐和子さんと小説家の高橋源一郎さんが対話をする中で、岸本さんは「翻訳とはものすごく深く読むということ」と言い、高橋さんは「人は書くときに同時に読んでいる。手は書きながら、目は読んでいる。」と言っていました。これはコピーにも通じる話ではないかと思います。人はコピーを書く時、同時にコピーを読んでいる。その読みの厳しさが、コピーのクオリティを決める。自分に厳しくなればなるほど、他人の基準に左右されることはなくなっていく。そのためにはたくさん書くのと同じくらい、たくさんコピーを読む必要があります。
コピー年鑑は、コピーをまとめて読むことの大きな助けになります。そこにあるのは審査委員たちがコピー年鑑に載せるにふさわしいと考えたコピーの集積。つまり、コピーライターたちが読むに値すると認めたコピーの集まりです。
コピーは選ぶことがいちばん難しい。いい眼を持った先輩の下についたり、いい眼を持ったクライアントに鍛えられたりする必要がある。でも、そんな幸運が誰にでもあるわけではない。だからこそ、コピー年鑑はあるわけです。
コピー年鑑にあるコピーを読む。そして投票結果や、審査員のコメントを読む。賛成してもいいし、反対してもいい。自分なりの眼を養うことに意味がある。そしてコピー年鑑を読む時のその厳しい眼で、自分自身のコピーを見返せば、コピーの質は格段に上がる。ここに、コピー年鑑の教育的な意義があります。
コピーは自分で上手くなれ、という今思えばとてもありがたい教育方針だったため、コピー年鑑をひたすら読むことから僕の修行は始まりました。分類や分析をすることなく、コピーそのものを無心になって読みました。このコピーが好きだ、と思うコピーは自然と覚えました。やがて、この人が書くものは好きだ、と思う人の名前を覚えていきました。その頃の記憶で、今も働き続けています。その頃の記憶だけで仕事していると言っても過言ではありません。