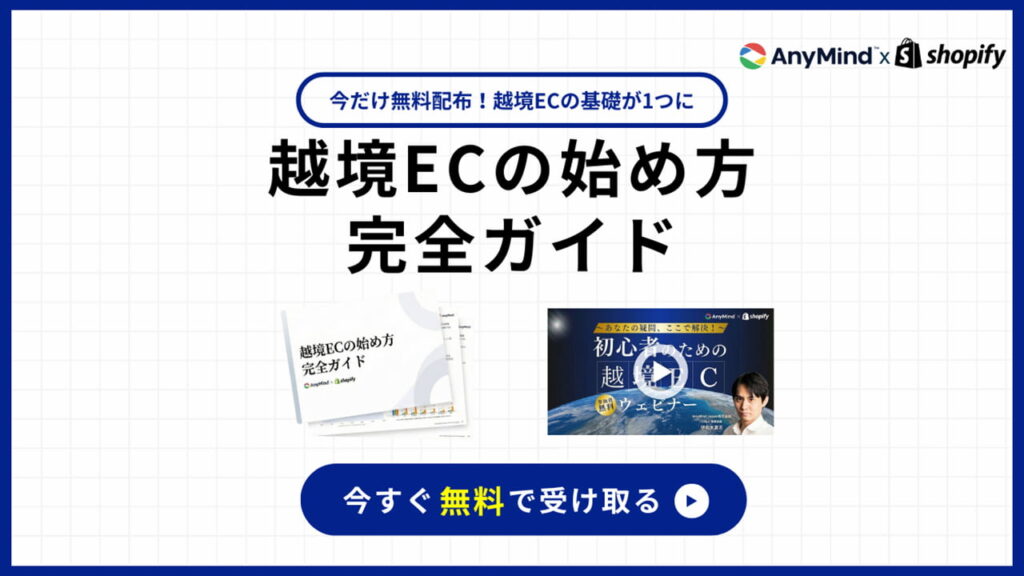※本記事は情報、メディア、コミュニケーション、ジャーナリズムについて学びたい人たちのために、おもに学部レベルの教育を2年間にわたって行う教育組織である、東京大学大学院情報学環教育部の有志と『宣伝会議』編集部が連携して実施する「宣伝会議学生記者」企画によって制作されたものです。企画・取材・執筆をすべて教育部の学生が自ら行っています。
※本記事の企画・取材・執筆は教育部修了生・黒田恭一が担当しました。
――サン・アドが設立された1964年当時の日本の広告業界はどのような状況にあったのでしょうか。
三好:取材の依頼を受け、社内の資料をあたり、設立当時のことを調べてみました。そしてサン・アドが設立された1964年に刊行された「TCC(東京コピーライターズクラブ)年鑑」の序文に、こんな言葉を見つけました。
当時のTCC会長だった上野壮夫さんが「毎日の広告のなかには、 たしかに新鮮で、ユニークで、人の心をゆるがす、すぐれたものがある。だが、その大部分は退屈で、手垢のついた、魅力のない、ありふれたもので占められていることも事実だ。」と書かれています。
当時はいざなぎ景気の真っただ中でしたので、おそらく日本の広告産業も活況だったのだと思います。興味深いのは、ここで上野さんが言われていることは現代の社会で広告に携わる私たちが抱えている課題と大きくは変わらないことです。
――開高健さんが、サン・アド「創立の言葉」を残しています。これを読むと、当時の広告業界に対するアンチテーゼのような表現が目立ちます。
三好:マーケティングブームに対する皮肉が感じられますよね。日本は、1955年からの約10年で、それまでアメリカが50年かけて構築したマーケティングの理論体系を一気にキャッチアップしようとしました。しかし本質を理解しておらず、ただマーケティング理論をふりかざして広告を語ることを多分開高は「おためごかし」と表現したのではないかと推察しています。
また創立の言葉の中に、
「美しくて上質でほんとに人びとの生活に役立つ製品があって訴求の方法に困っていらっしゃるのでしたら電話してください。」
という文章が出てきます。出来が良い製品にしか広告は効かない、出来がよろしくない製品を広告で助けようとしてもすぐにメッキがはがれて効かなくなるんだということを、売れっ子クリエイターの開高は理解していたので「いい製品」のある生活を提案することを大事にしたい、と主張しているんですね。
――発足当時の精神のなかで、今でもサン・アドのDNAとして受け継がれているものはありますか。
三好:当社は1964年にサントリー宣伝部から独立した企業ですが、当時のサントリーの佐治敬三社長から言われたミッションは、「サントリーだけでなく、日本全体の宣伝を盛り上げてくれ。」だったと聞いています。その命を受けて、設立の際に開高が作成した「創立の言葉」の中で、サン・アドの存在意義は
「その生活にほんとに役に立つ」
と記されています。これが設立以来、継承されるDNAだと思います。