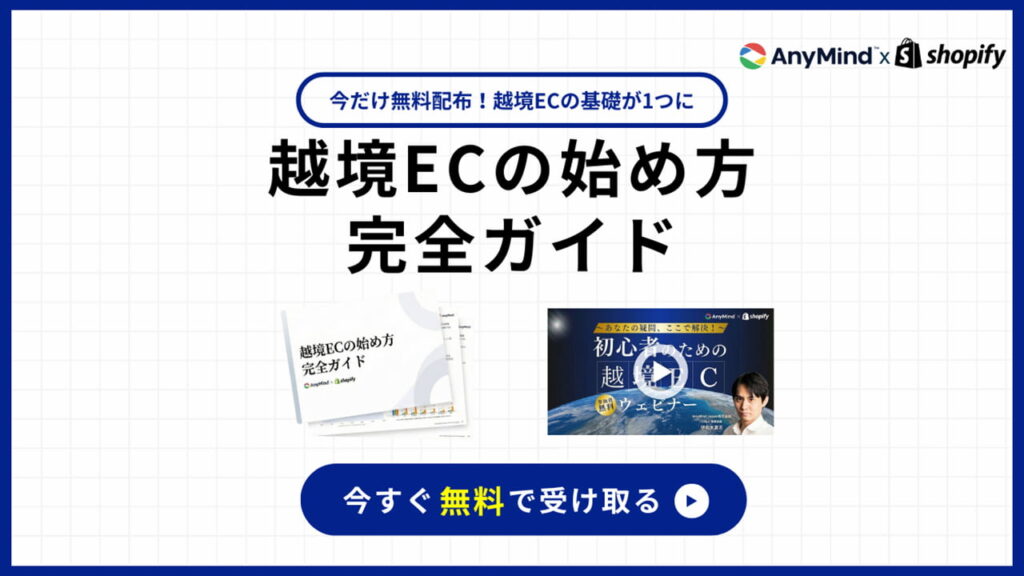本書の著者・杉山恒太郞氏は、長く広告の世界で活躍し、小学館のピッカピカの一年生、サントリー・ローヤルのランボーシリーズなど、記憶に残る名だたる広告を手掛けてきた制作者であるが、かつて「広告」の世界がなにか身にそぐわないと感じていた時期があったと伺ったことがある。広告が声高になり、ひとりよがりの自己主張に陥っているように感じ、心底広告が疎ましく思われたときがあったという。そんなときに「消費の歯車を回転させる日頃の業務への後ろめたさから、社会正義に目覚めて思いつきで制作する腕試しのような仕事」に思えた「公共広告」と接点を持ち、やがてその奥深さに気付くに到り、著者は目を啓かれた。「公」の視点を内包することで、著者はそれまでの自らの広告感が改められ、真に広告に対して自由になれた、それゆえ公共広告は「クリエイターとして再出発するきっかけをくれた恩人のような存在」だとまで言う。「消費の歯車」のくだりは、多分に自嘲的で話半分で聞く注意は必要だが、本書の中心を成す、この30年の世界のトップクリエイターたちの手になる「世界を変えた公共広告」の紹介ページを繰りながら追体験し、それぞれの作品に添えられた著者の見解を読み進むことで、著者を再生させたTHINK PUBLICの重要性がじわじわと心に響いてくる。
ドラッグ、海洋ゴミ、新型コロナ、戦争……、公共広告が課題とする対象は幅広い。受け手は「自分には関係ない」というのは簡単だ。しかも「人間は気持ちよく説得されたい生き物で、説教には反発する」と著者は言う。では、どうするか。これは他人事ではありませんという、ある意味、耳に痛い事象に目を背けさせず、関わりを持たせ、そののっぴきならなさに気付かせ、最終的にはアクションに結びつけるためにはクリエイターの力量が試される。テーマによっては、本来広告が扱うべきでないとされてきた人間の暗部にまで表現は踏み込まざるを得ない。こうした世間の価値観をアイデアと表現で転換するという取り組みは、挑戦しがいがあるとして広告界のトップクリエイターたちが競い合う分野にもなったという。