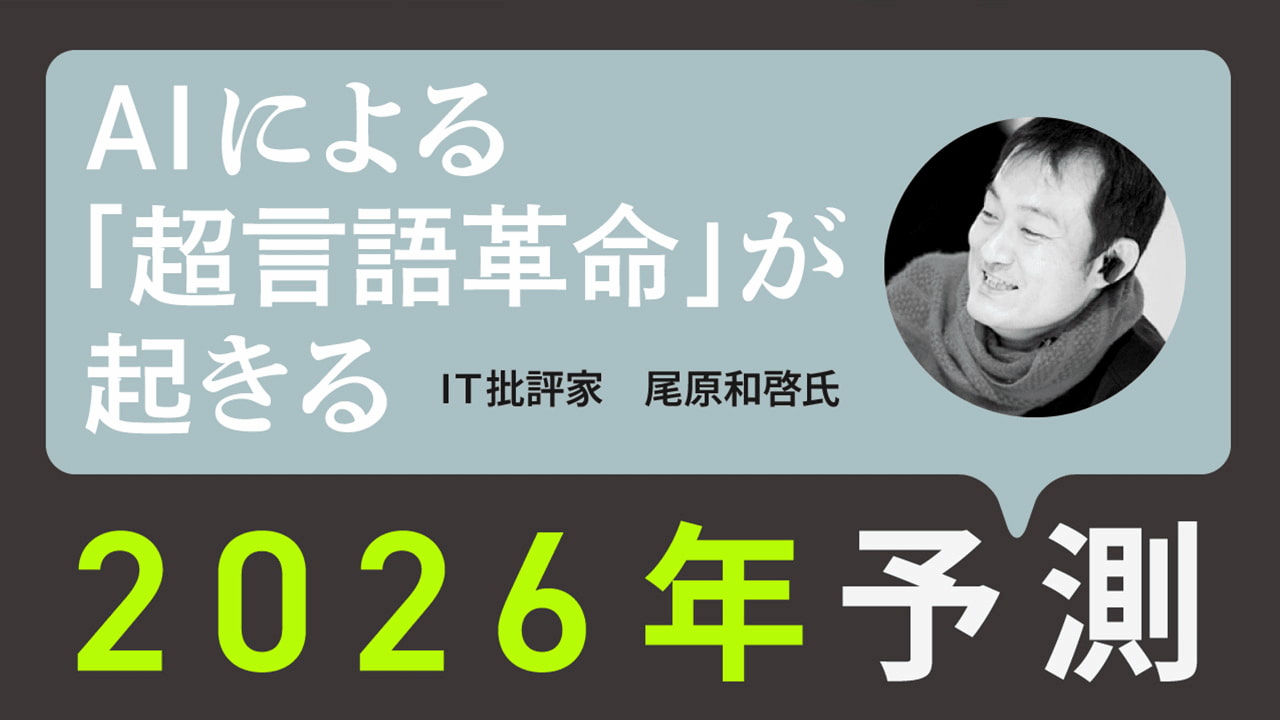現代社会は、AIという新たなテクノロジーによって、大きなパラダイムシフトの渦中にある。インターネット革命、スマートフォン革命に続くこの変革は、私たちの働き方、創造性、そして社会のあり方そのものを根底から覆す可能性を秘める。
この歴史的な転換点を、私たちはどう捉え、未来に向けて何を準備すべきなのか。今回は『アフターデジタル』(藤井保文氏との共著)などの著書で知られるIT批評家の尾原和啓氏に、AIがもたらす変革の本質と、これからの時代に求められる人間の役割について、語ってもらった。
AI革命はインターネット以上。レベルの違う変革が始まる
これまでのインターネット革命やスマートフォン革命と比べて、今回のAIがもたらす変化はどのくらい違うのか。私は、明らかに、そしてレベルが違う変革だと捉えています。
インターネットは情報の流通コストをゼロにし、スマートフォンはその情報へのアクセスを遍在化させました。しかし、これらはあくまで「アクセスを楽にする」という話でした。
対してAIは、そのつながりを価値に変える力が、指数関数的であるだけでなく、無限大にまで発散する可能性を秘めています。Googleの創業者たちも関わる「シンギュラリティ・ユニバーシティ」で語られているように、「AIが自律的に自らを良くする(自己改善)」世界が議論されています。毎日1%の改善でも、休むことなく1年間続ければ40倍になる。これが100万台のAIで起これば、もはや人間の認知を超える速度で進化してしまうのです。
エリック・シュミット氏(元Google CEO)は人工知能の影響を火や電気のような変革的な発明に例え、ビル・ゲイツ氏は「AIはインターネット以上の発明だ」と語るように、この変革の大きさはシリコンバレー界隈ではコンセンサスになっています。
産業革命が肉体を外部化したように、AIは脳すら外部化させる
AIがなぜそれほど大きな変革をもたらすのか。それは、知性の生成コストを下げるだけでなく、自己の機能を外部化できるからです。産業革命が肉体労働を機械に外部化させたように、AIは私たちの「脳」すら外部化させてしまいます。
これは、人類が「言語を獲得した」レベルに匹敵する変革だと私は考えています。
イーロン・マスク氏が設立した脳インプラント開発会社「ニューラリンク」は、まさにその象徴です。脳と機械を直結させるこの技術は、すでに人体での治験が進んでおり、思考するだけでタイピングができる段階にまで来ています。
マスク氏に言わせれば、人間のコミュニケーションは、脳という高次元で考えていることを、喉を使って「言語」という低次元なものに落とし込んでいるに過ぎません。脳の信号とAIが結びつくことで、私たちは言語の制約から解放され、脳内のもっと高次元な思考を高速で伝え合えるようになるかもしれないのです。
AIは言語化できない感覚すら認識している
近年のAIの進化は、私たちの想像をはるかに超えています。ChatGPT-5やGemini 3などをトレーニングしている最新のチップは、音や画像を、もはやテキストのタグを介さずに、音や画像のまま学習しています。
これは何を意味するかというと、AIは「言語化されていない音の感覚」や「言語化されていない画像の感覚」すら認識できるようになった、ということです。
例えば、虹の色を日本人は7色と捉え、アフリカのある地域では3色と捉えるように、言語は世界を分節します。しかし、本来の虹は何色にも分解できる連続スペクトラムです。AIは色を何万次元というベクトルで認識するため、人間が「白」という一言で済ませてしまう色でさえ、無数の違いとして捉えることができます。
さらに、その無数の色の違いと、それを見た人間がどういう感想を抱くかを関連付けて学習している。つまり、AIは芸術家が持つ色のニュアンスの把握能力以上の解像度で、世界を見ているのです。
写真がアーティストを生んだように、AIは新たなクリエイターを生む
このAIによる変革を歴史にたとえるなら、私は「写真」と「活版印刷」の発明に近いと考えています。
写真が登場したことで、写実的に絵を描くという価値は写真に移行しました。その結果、それまで肖像画家として写実性を追求していた人々は、自らの主観(センス)を描く「アーティスト」へと転身を迫られました。印象派の誕生です。正確な風景画の代わりに、モネやルノワールは「自分には光がこう見えた」「空気は紫色に感じた」という主観を描き、それが現代のアート市場につながった。結果として、肖像画家の産業よりもずっと大きなアートという産業が生まれました。
これと同じことが、生成AIによって起きるでしょう。誰もが動画を、音楽を、画像を作れるようになる。これまでセンスはあっても、表現するためのスキルがなかった人々が、自分の見ている世界をそのまま届けられるようになります。
AIは平均値を出す道具ではない。人間のセンスを拡張する壁打ち相手
「AIは平均的なものしか作れない」という声をよく聞きますが、それは大きな誤解です。AIが平均的な答えを出すのは、プロンプトを入力する人間が平均的な問いしか投げかけていないからです。スコープの切り方次第で、AIはいくらでもエッジの効いた答えを出してくれます。
その最たる例が、アニメ『チェンソーマン』の音楽制作で使われたソニーコンピュータサイエンス研究所が開発したAIツール「ChainsawGAN」です。サウンドトラックの作曲家である牛尾憲輔氏が作った打楽器のリズムパターンをベースに、AIが「もっとこういうパターンがある」と拡張しまくる。作家はその中から「これは良い」「これは違う」とフィードバックし、さらにエッジを尖らせていく。
さらにすごいのは、「これは良い、悪い」と評価する作家のセンスそのものをコピーしたAIモデルまで作ったことです。突拍子もないアイデアを出すAIと、作家のセンスを学習したAIが、作家が寝ている間も延々と壁打ちを続ける。そうして、今までにないけれどセンスは通っている、という新しい音楽が生まれたのです。
AIは、スキルがない人でもセンスを発露できる道具であると同時に、センスを持つ人の表現を拡張し、新しい領域へと飛ばしてくれる最高の壁打ち相手なのです。