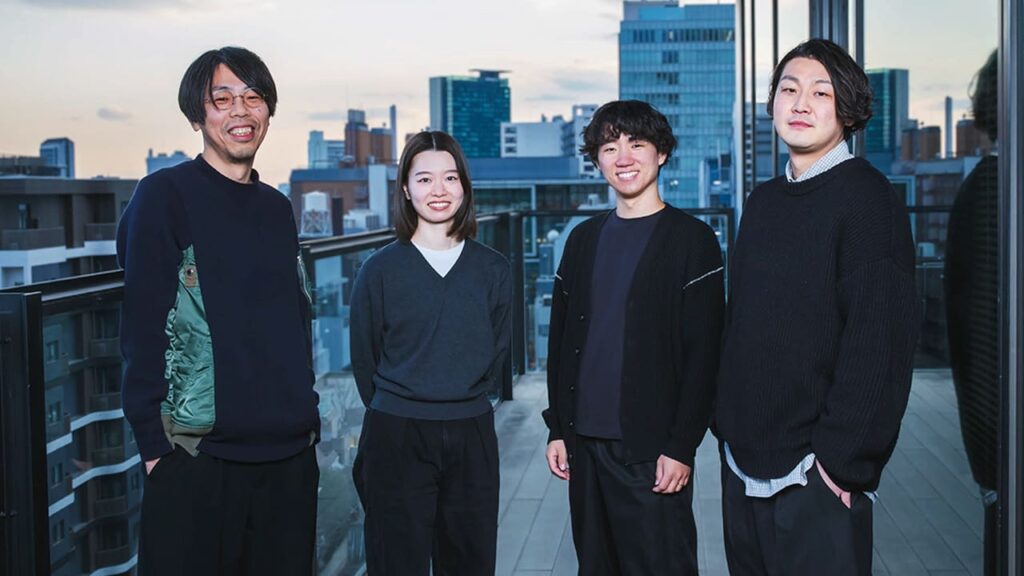「墓じまい」という言葉が一般化して久しい。人口減少、高齢化、継承者不在。理由はさまざまだが、墓を維持できなくなり、先祖代々の墓を閉じる選択をする人は確実に増えている。
多くの場合、墓じまいは「仕方のない合理的な判断」として語られる。私はこの墓じまいという行為の中に、従来の社会構造の限界が極めて凝縮された形で現れていると感じている。
本稿では墓をどう畳むか、そして縁をどう残すかという視点から「墓の縮充」を考えてみたい。
墓じまいで、本当に失われているものは何か
私は2024年に島根県隠岐郡海士(あま)町から依頼を受け、墓地の実態把握調査を行った。 調査の背景には、町として以前から抱えていた切実な課題があった。
海士町では近年、管理が行き届かなくなった墓地が散見されるようになっていた。継承者が島外に移り、長期間手入れされない墓が増え、景観の悪化や、隣接する区画の利用者に負担がかかるといった問題が顕在化していたのである。町としても対応策を検討する必要に迫られていたが、墓の問題は制度や設備だけで整理できるものではない。宗教観や家族観、先祖への思いが複雑に絡むため、拙速な制度設計はかえって分断を生みかねない。
そこでまず必要とされたのが、「今、町の墓地で何が起きているのか」を正確に把握することだった。その第一歩として、町内に点在する墓地の現状を調査し、地域内外の関係者の声を丁寧に集める必要があった。町内に点在する墓地を一つひとつ歩いて回り、墓の状態を確認するとともに、区長(編注、自治会長)をはじめとする地域内の住民、そして現在は島外に暮らしながら海士町にゆかりを持つ人たちへの聞き取りを重ねた。調査の中で、繰り返し耳にしたのは、意外にも「遺骨を島外に持ち出したいわけではない」という言葉だった。
ここで、海士町の地理的な条件についても触れておきたい。海士町は島根県沖、日本海に浮かぶ隠岐諸島の一つ・中ノ島に位置する。東京からは飛行機と船を乗り継いでおおよそ半日、大阪からでも鉄道とフェリーを使って5〜6時間を要する。本土側の港から島へ渡るフェリーは片道およそ3時間。天候によっては欠航や遅延も珍しくなく、「少し墓を見に帰る」という感覚で往復できる距離ではない。