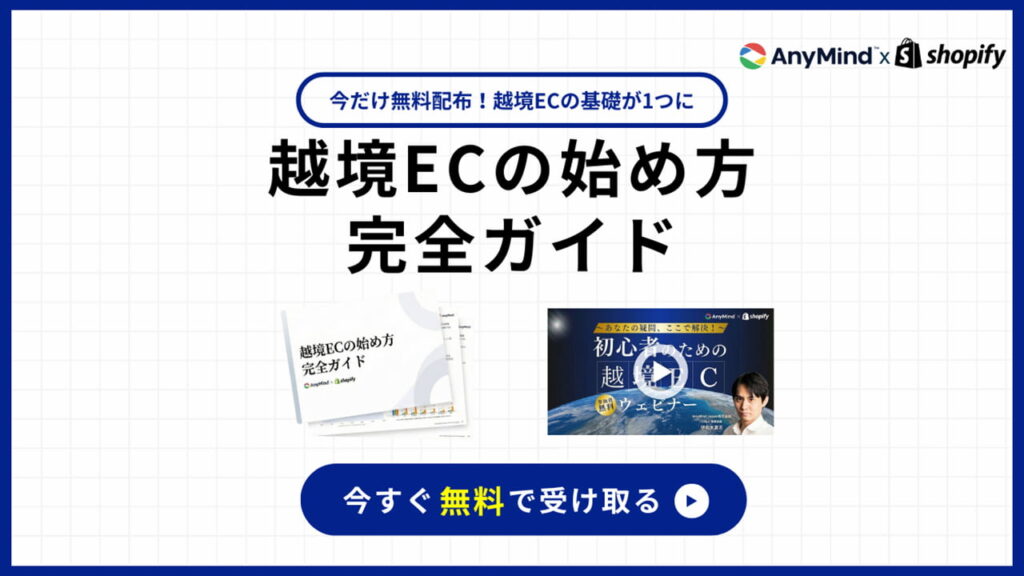35年通用する、糸井重里さんのコピーができた理由
何気なく古いコピー年鑑を懐かしくめくっていたら、目がテンになった。これって昔の広告でしょ。でも、今書いても通じるキャッチじゃない!?
「いま、どのくらい『女の時代』なのかな」。
西武流通グループの1980年に出稿された新聞全10段の広告だった。新郎は羽織袴、花嫁は文金高島田に打掛姿。金屏風の前で御仲人を左右に従えてご挨拶という情景写真。昔の結婚式ってこうだったのだな、と感慨深い。
「いま、どのくらい」と書いていることは35年前にすでに「女の時代」だったということになる。ボディコピーでも、「『女の時代』という言葉は、すっかりなじみの深いものになってきましたね」と、糸井重里さんは書いている。
そうなると、ずっと前から「女の時代」だったということになる。でも未だに、少ししか「女の時代」になっていないから、2015年に安倍首相が「女性活躍推進法案」を作って、女性の登用割合を公表する義務まで作ったのだろう。「いま、どのくらい『女の時代』なのかな」という西武流通グループの広告はこれから3年後も、5年後も使えることになりそうだ。
この原稿の制作裏話として糸井さんは、実は最初の提案時点では「このフレーズではなかった」と言っている。提案は「人材、嫁ぐ。」というキャッチフレーズだった、と。このフレーズだってうまいと私は思った。惜しい戦力が結婚退職してしまう、しかし西武流通グループは復帰制度を整えてカムバックを歓迎します、ということを趣旨に落とし込むのだから。しかし、当時の社長の堤清二さんに拒否された。「女性にとっての結婚は、人生のなかのもっとも個人的でとても大きな選択です。それを企業の論理で、人材が嫁いで行くなどと表現するのは、あまりにも失礼でしょう」と。堤さんの「個人は個人として評価されるべきであって、『企業の機能の一部分』として評価されるべきではない」というメッセージを糸井さんは重く受け止めて、先のキャッチフレーズになったという。
社長直々に広告をプレゼンする機会はめったにないことだが、企業広告は社の理念を代弁するわけだから、オーナー企業の場合は特に、経営者の思想とか、哲学とか本音とか、人間性とか趣味とか、日頃から汲み取っていくことが要求される。
社長堤清二さんは文人堤清二、いえ、文人辻井喬さんでもあるから広告会議は大変だったことだろう。フェミニスト的発言は経営者というより、辻井喬の顔が伺える場面であった。糸井さんは今でも堤さんの言葉に影響を受けているという。
人の記憶に残る広告の「コトバ」の力
私がこの西武流通グループの広告に引っ掛かったのは「いまでも通用する広告」であるということであるが、つまり、それは「コトバ」に惹きつけられたことに他ならない。映像ではない。タレントでもない。

長年人の心に残っている広告は、キャッチフレーズで記憶されている。飲み会などで「ビールを何にする?」と聞くとサッポロファンは「男は黙ってサッポロビール」という人がいる。これは1970年の広告であったが、未だに浸透しているコトバだ。トリスウイスキーの「『人間』らしくやりたいナ」、は1961年の広告だった。この広告を見たことがなくても、このコトバを何かの折に聞いたことがあるだろう。くしゃみをたて続けにすると「クシャミ3回ルル3錠」と声がかかる。1回あたりの錠剤の数を歌いこんだだけのフレーズであるが、古典的普遍的名作となって覚えられている。
「女性よ、テレビを消しなさい」。社会評論家の大宅壮一さんがテレビ漬けの日本社会に対して一億総白痴化と憂いた時代、角川文庫はこのコトバで女性を叱咤した。この広告は強烈だった。未だに引き合いに出されるアートディレクターの石岡瑛子さんの作品であるが、もう一度この広告を掲載してもらいたいくらいだ。
日々たくさんの広告が作られ、ヒットしたものもあるだろう。話題となったものも数多くあるだろう。でも、すべては残らないで忘れ去られていく。
商業的に貢献したから役目は果たした、という考え方はもちろん正当である。でも、その時のキャッチフレーズが人口に膾炙(かいしゃ)して生き残っていくとしたら、何十倍にもお役に立っていることになるのではないか。これは企業の財産の一つになるといってもいい。
記憶に残り、人の口に上り、伝えられていく「コトバ財産」を分析すると、それらが財産になったのはコトの真理をついているからだと思う。なるほど、そうだそうだ、と納得させられるから記憶に残っていくのだろう。電波で霧消し、八百屋の野菜の包み紙で捨てられても、人の記憶に残る「コトバ」を書きたいものだ。
脇田直枝
コピーライター。元電通EYE社長。
早稲田大学卒業後、フリーを経て電通入社。男社会の牙城だった広告業界で女性だけの広告代理店、電通EYE を設立、代表取締役を務めた。集英社『COSMOPOLITAN』創刊時、「この雑誌には、エクスタシーがある」という広告コピーをはじめ、国鉄、サントリー、松下電器、など数多くのキャンペーンを手がけ、時代時代で女性たちを鼓舞し、牽引してきた。2000年東京都「第2回男女労働者に優しい職場推進企業 能力活用特別賞」、2001年モンブラン社「第1回ビジネス・ウーマン・オブ・ザ・イヤー賞」、2003年「第43回日本宣伝賞吉田賞」など受賞。