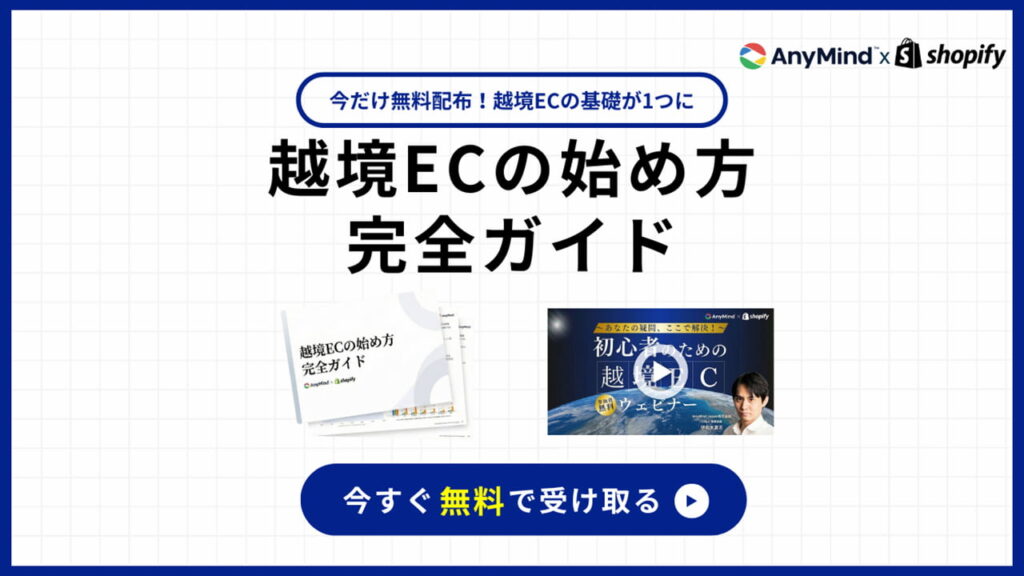蔓延する「負のストーリーテリング」
誰もが並々ならぬ興味を抱いているにもかかわらず、公の場では口にできないもの。それが「性」という領域だ。政治家や芸能人の不倫、セクハラや児童買春、ジェンダーを扱ったCM動画の炎上など、テレビや週刊誌、SNSのタイムライン上では、常に誰かの性にまつわる言動やトラブル、それらに関する批評や論争で賑わっている。
メディアの世界では、コンテンツの見出しや文面に性的な要素や文言を絡ませれば、容易に注目される(もしくは関心を引く)ことができる(と考えられている)。
一方で、性を絡めたコンテンツは飽きられるのも早い。AV女優の職業寿命が、場合によってはデビューからほんの数カ月で尽きてしまうように。そして性を扱うこと・売りにすることに伴うスティグマも同時にのしかかる。言うなれば、メディアにおける性は、副作用の強い「ドーピング」のようなものだ。
私の働いているNPO業界でも、そうした「ドーピング」を活用して、社会問題に対する世間の認知度を高めようとする試みは以前から行われている。例えば子どもやシングルマザーの貧困に対する社会的認知度を高めたい場合、ただ当事者の経済的貧困の状況を描写するのでは、メディアの話題にはならない。
「JKビジネスで性的に搾取される貧困少女」「性風俗店で子どもの養育費を稼ぐシングルマザー」といったように、性的な要素を絡ませてセンセーショナルに物語化することで、「バズらせる」ことが可能になるわけだ。
一方で、そういった試みに対しては批判も多い。一時的に注目されるだけで、根本的な問題解決にはつながらないケースが少なくないからだ。
性を絡めて「バズらせる」行為は、あくまで最終的な到達目標(NPOであれば政策提言や立法など)を見据えた戦略の中の一つの手段として、目標を明確にし、期間を限定した上で行われるべきである。
そうした戦略が欠如したまま、センセーショナルな物語化によって注目される手段が自己目的化してしまうことを「負のストーリーテリング」と呼ぼう。
「出版業界に消費されたくない」
出版業界においても、近年「負のストーリーテリング」が看過できないレベルで散見される。
例えば、一人ひとりの当事者に寄り添いながら地道に活動しているNPOの活動を、当事者の悲惨なエピソードや煽情的な部分だけを切り取った「貧困ポルノ」に仕立て上げ、当事者に対する社会的なスティグマを増幅させるようなタイトルをつけて書籍化するケースも見受けられる。
こうした「負のストーリーテリング」は、売上至上主義の帰結として批判されがちだ。しかし逆説的に考えれば、「負のストーリーテリング」は売上至上主義の徹底によって生じたものではなく、売上至上主義の不徹底によって生じたものではないだろうか。
売上至上主義の立場に立つのであれば、「負のストーリーテリング」は必ずしも売れるための条件ではない。
著者や当事者の反対を押し切って、“売らんかな”の煽りタイトルや見出しをつけたものの「結局増刷がかかりませんでした」「PVが伸びませんでした」という例は、掃いて捨てるほどあるはずだ。結果として、著者のブランド価値を毀損するだけ、読者離れを招くだけになってしまう。

アカデミズムの世界でも、若手の研究者の中には「出版業界に消費されたくない」と語る人は少なくない。修士論文や博士論文に煽りタイトルをつけて新書化したものの、一時的な話題になっても、その後が続かない。
場合によっては出版が逆効果になり、就職先も決まらない。そうした先達の「犠牲者」の姿を見ていれば、「出版はちょっと……」と思う人が増えるのは必然だろう。
必要なのは中長期的な戦略
私が初めて出版した書籍は、自身の起業ストーリー(障害者に対する射精介助事業の展開)を題材にした新書だった。
執筆当初は、『ベーシック・セックス社会』というタイトルを想定していた。ベーシック・インカムになぞらえて、全ての人が最低限度の性の健康と権利を享受できる社会にしよう、というソーシャルなメッセージを込めたタイトルだ。
しかし「それでは売れない」ということで、最終的に『セックス・ヘルパーの尋常ならざる情熱』という奇天烈なタイトルに変更されることになった。書籍の本文中では「セックス・ヘルパー」などという言葉は一度も使っていない。
「頼むからそれだけは勘弁してください」「人に絶対言えないタイトルじゃないですか」と泣きたくなったが、結局編集者に「これで行かせてください」と押し切られ、このタイトルのまま刊行することに決まった。
どうなることかと思ったが、タイトルのインパクトもあって各種メディアで話題になり、無事増刷もかかった。デビュー作が売れたおかげで、その後も継続的に出版のオファーを頂けるようになった。
結果論にすぎないかもしれないが、私のデビュー作に関しては「社会的な切り口で性の問題を論じるスタイルの新書を今後も刊行できるようにするため、煽りタイトルをつけて全力で売る」という戦略は成功だったと言える。
この成功がなければ、その後の『はじめての不倫学』や『性風俗のいびつな現場』などのスマッシュヒット(いずれも3万部台)も生まれなかった。
ストーリーテリングに必要なのは戦略である。もちろん、戦略は必要条件にすぎず、十分条件ではない。私の本も、たまたま運よく売れただけだ。しかし、戦略なくして売れることはほとんどない。どんな標的も、狙わなければ当たらない。
現在の出版業界は、医療否定本や嫌韓・嫌中本、コピペだらけの自己啓発本のように、「読者が感情で釣られることを前提にして、その上で売れる本をつくろう」という競争になっている側面は否めない。
しかし、そうした競争に参加したところで、中長期的には良い本は生まれない。炎上商法まがいの手口で書き手を消費し続ける悪循環に陥ってしまえば、次世代を担う著者は決して育たない。読み手も先細りする一方だろう。
必要なのは、戦略と理性に基づいた本を書ける著者、及びそれを享受できる読み手を育てていくことだ。こうした地道な土壌の整備が、戦略なき「負のストーリーテリング」の蔓延を抑え、結果的に真の意味での売上至上主義=出版業界の隆盛につながると私は考える。
本記事は、『編集会議』2017年秋冬号に掲載されているものです。

一般社団法人 ホワイトハンズ 代表理事
坂爪真吾 氏
新しい「性の公共」をつくるという理念の下、社会的な切り口で現代の性問題の解決に取り組んでいる。著書に『性風俗のいびつな現場』(ちくま新書)など。