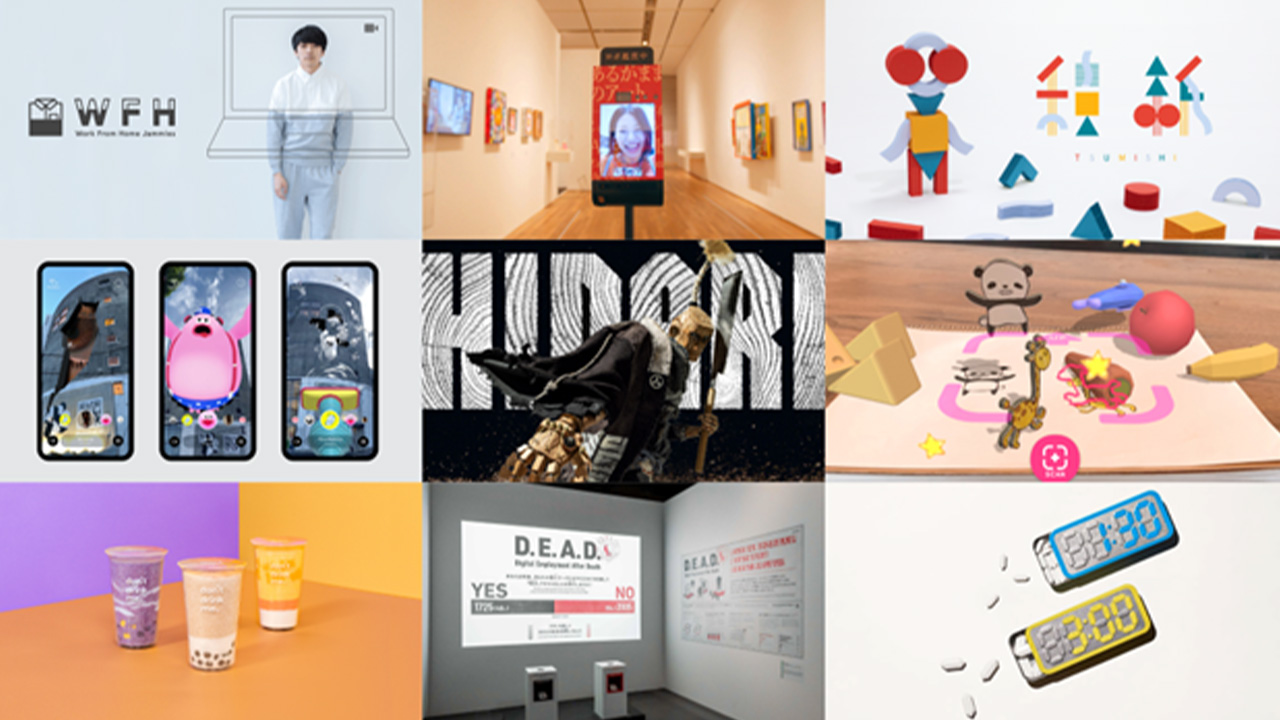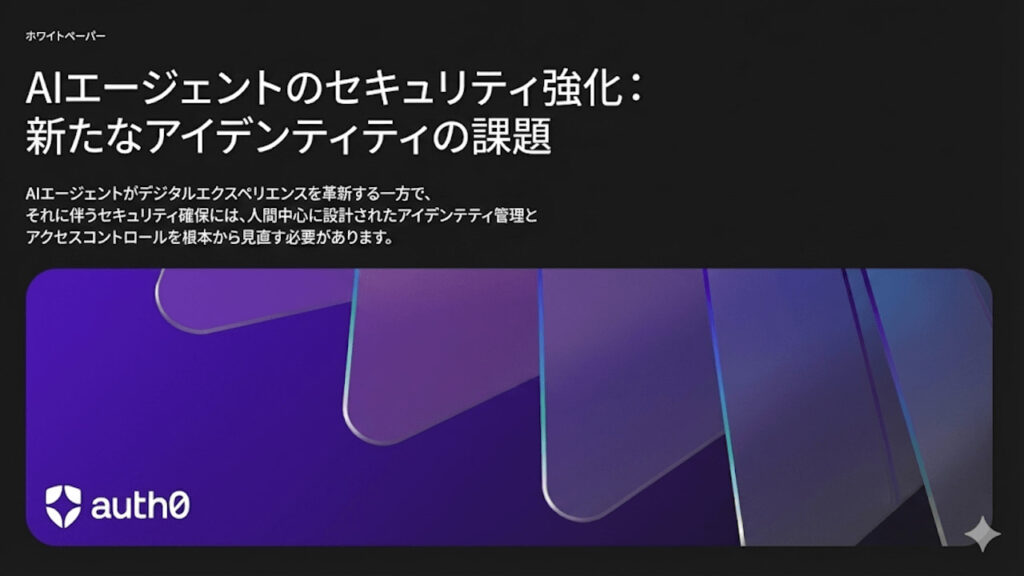クリエイティブスタジオ・WhateverのCCO、川村真司氏による寄稿・第2回。今回のテーマは、なぜWhateverは自社プロジェクトに力を注ぐのか? Whateverのノウハウを公開する講座「How to make Whatever」と連動し、アイデアを継続的に生み出すための文化と仕組みを紐解いていきます。
こんにちは。WhateverのCCO(チーフ・クリエイティブ・オフィサー)の川村真司です。前回の記事では、僕たちが「なんでもつくる」ために整えている三位一体のチーム体制についてご紹介しました。
前回の記事
今回は、Whateverの大きな特徴でもある自社プロジェクトについてお話ししたいと思います。
エンターテインメント業界のみならず、あらゆるビジネスの現場で「IP(知的財産)」という言葉が当たり前のように使われるようになりました。この流れは、クライアントの依頼を起点にものづくりを行う「受託制作」に軸足を置いてきた、僕たちのようなクリエイティブスタジオにも押し寄せています。
広告、映像、デジタルプロダクション──。あらゆるクリエイティブの領域で、単に誰かの課題を解決するだけではなく、自分たち自身が核となるコンテンツやプロダクト=IPを持つことが、表現の自由度やビジネスの持続性に直結する時代になってきました。
そうした変化の中で、Whateverはクライアントワークという基盤の上に「自社プロジェクト」、つまり自分たち自身のオリジナルIP開発に力を注いできました。僕たちにとって自社プロジェクトは、クライアントワークだけではたどり着けない地平に踏み込むために欠かせない取り組みになっています。
なぜWhateverが自社プロジェクトに情熱を注ぐのか。その理由と背景にある僕自身の考えをお話しできればと思います。
クライアントワークで感じていた「見えない壁」
広告やデザイン、映像制作などの仕事は、クライアントから与えられた課題を解決する「受託制作」が基本です。これらはとてもやりがいがあり、社会的な価値も高い仕事です。ただ、長年この世界に身を置くなかで、クリエイターとして常に「見えない壁」を感じていました。
こうした受託の仕事には、予算の制約、ブランドイメージ、ターゲットの特性といったさまざまな制約が伴います。どれだけ「これまでにない、誰も見たことのない表現を生み出したい」と願っても、クライアントのゴールが必ずしもそこにあるとは限りません。目の前の商品やサービスを届けることが広告やデザインの至上命題だとしたら、斬新すぎるアイデアはリスクでしかない。それは当然のことで、僕たちもその現実を理解しています。
けれど、ものをつくる人間としては、まだ誰も見たことのない表現や誰も触れたことのない体験にこそ世界を少し前に動かす力があるし、世界中の誰もが同じように驚き、共感できる強さを持っているとも信じています。そんな時、やはりこうしたクライアントワークならではの制約が壁になってしまうことも事実です。
このジレンマこそが、僕たちが乗り越えなければならない壁でした。