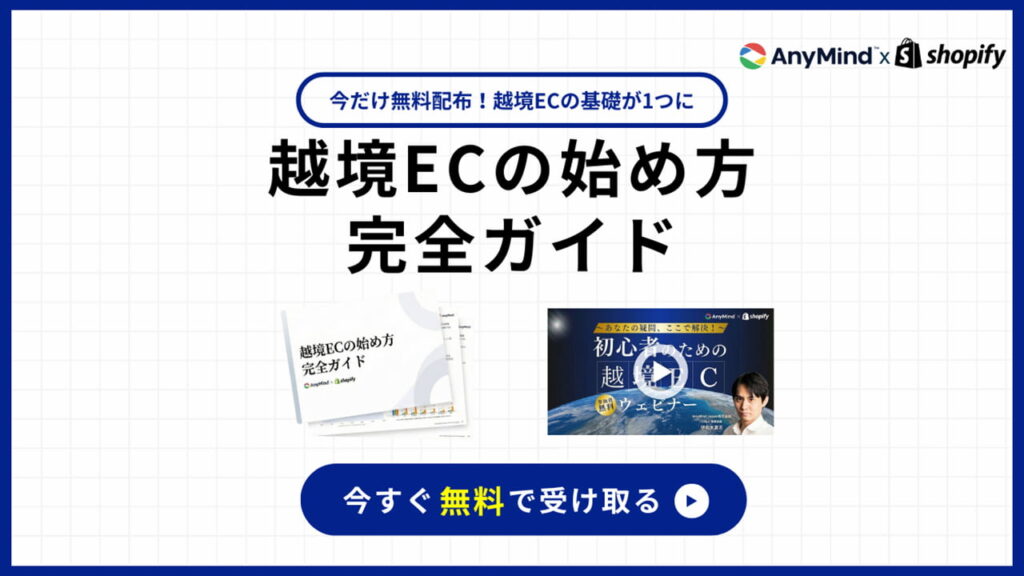この記事の講師
橋本 純次(はしもと・じゅんじ)
社会情報大学院大学 広報・情報研究科 専任講師
東北大学 大学院情報科学研究科修了。博士(学術)。社会情報大学院大学助教を経て、2020年度より現職。専門はメディア文化論と公共政策。主な研究領域として、放送政策、民放地方テレビ局、オーディエンス研究など。
筆者は、メディアやコミュニケーションを専門とする、いわゆる文系の研究者である。普段は、オーディエンスがどのようにテレビを観ているか、また、それを前提としたメディア企業や政策のあり方はいかなるものか、といった事柄について、「人口移動」や「空間」といったキーワードと関連付けながら考えている。
こうした、ある種「平和な世の中」を前提とした研究や研究者は、近年多発する地震や台風といった自然災害のなかで、自らがいかに無力かを痛感することが少なくない。今般の状況についても同様である。しかしながら、各自の専門性に基づいて非常事態を分析・言語化し、後世において参照可能な形で記録することは、我々に課せられた使命のひとつであると考え、筆を執った次第である。
コミュニケーションの基本は、相手方の特性や状況を適切に見定め、対象に応じた方法で対話を試みることにある。特に、科学技術に関するリスク・コミュニケーションは、危機が発生していない「平常時」、危機発生直後の「非常時」、危機から復興しつつある「回復期」という3種類のフェーズに応じて戦略的に行うことが必要である
*1
。本稿では、新型コロナウイルス感染症の非常時・回復期におけるテレビ報道のあり方について検討する。
感染症に関する報道の失敗
本稿は、テレビ報道の質について意見を述べるものではない。各局とも限られたリソースのなかでコンテンツを制作しており、かつ総括する段階にない状況において、そこに批判的な目線を向けるのは生産的ではない。
一方で、現段階で指摘せざるを得ない失敗も存在する。すなわち、感染症に関するニュースの「構造」、平たくいえば、画面構成や映像のつくり方が、初期段階において「平時のニュース」とまったく同じだったことである。
多くの視聴者が既に気づいている通り、ワイドショーやニュース番組のつくり方には「お約束」が存在している。政府や自治体の会見、街の声、スタジオで受ける時間のバランスはどれくらいが適切か。専門家をスタジオのどこに配置し、どれくらい話を聞き、どれくらいの時間で次のニュースに進めばよいか。番組制作の効率化を進めるなかで、こうしたテクニックが各社で継承されているのである。