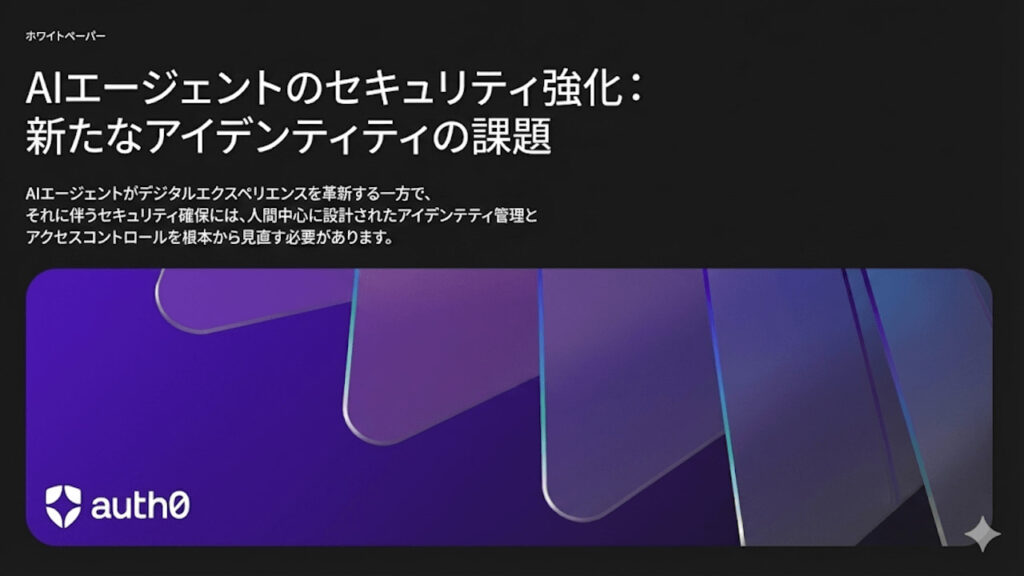娯楽を超えた日本文化コンテンツ 「感情資産」として存在
日本の文化コンテンツ産業は、単なる娯楽を超えて、いまや国や地域の「感情資産(emotional asset)」(ポジティブな記憶)を形成する存在になっている。この連載で辿ってきたアニメ、音楽、ゲーム、映画、スポーツ、さらには食文化まで――。そのどれもが「個人の記憶」と「社会の物語」を結びつける回路として機能している。
近年、海外市場でも注目されているのは、こうした日本的コンテンツが「消費される文化」ではなく、「共有される文化」として再定義されつつある点だ。SNSやストリーミングが浸透したことで、作品は単体で完結せず、ファン同士の語りや「巡礼(聖地訪問)」などを通じて新たな価値を生み出している。
それは、マーケティングの言葉で言えば「共創型ブランド(co-creation brand)」であり、コンテンツが「場」として機能する段階に達しているということだ。このような状況を「文化資本の資産化」と呼ぶならば、日本エンタメは世界のなかでも最も成功した例のひとつである。コラムの第1回から第5回までで取り上げてきた事例に共通するのは、「共感を媒介にした価値の持続性」であった。
「ストーリーの地産地消」が生むブランド循環
地方発のアニメや映画がその地域の観光を活性化させた例は枚挙にいとまがない。埼玉・秩父市の『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』、富山・上市町の『おおかみこどもの雨と雪』、岐阜・大垣市の『聲の形』――いずれも作品と土地の間に「相互物語関係」を築いた。
この関係は、単にロケ地を巡るファンの移動ではなく、「物語が地域に帰化していく」プロセスだ。自治体はその物語性を観光PRや教育活動に応用し、地元住民が誇りを再認識する。結果として、「地域イメージ → ファンの感情 → 継続的関与 → 経済効果」という循環が成立する。
この現象は、いわば「ストーリーの地産地消」だ。地域の風土や方言、食文化、地形が作品世界に組み込まれ、グローバルな消費のなかで「ローカルのリアリティ」がブランド価値として立ち上がる。これはマーケティングの原則で言えば「差別化」ではなく「固有化(indigenization)」の戦略である。つまり、他と比べて優れているから選ばれるのではなく、そこにしかない物語があるから選ばれるのだ。
『聲の形』は作中に岐阜・大垣市をモデルとする風景が多く登場する。
大垣観光協会提供
音楽とスポーツがつくる「共感経済圏」
音楽とスポーツは、エンタメ産業のなかでも特に共感装置としての力が強い領域だ。たとえばKing Gnu、YOASOBI、Official髭男dismといったアーティストは、都市の風景や世代の感情を象徴化する存在として機能している。彼らの楽曲は、リスナーの「個人的記憶」を引き出しつつ、社会全体のムードを可視化する――これが「感情資産」の中核である。
一方、スポーツの側でも同様の動きが見られる。JリーグやBリーグのクラブは、地域のアイデンティティとファン・コミュニティを結びつける「社会ブランド」として成長している。たとえばサッカーJリーグの川崎フロンターレが地元商店街と連携して行う商業・文化イベント、楽天が運営するヴィッセル神戸を通じて展開する都市ブランド戦略などは、スポーツを媒介にした都市マーケティングの先端例である。
音楽とスポーツが共鳴するのは、いずれも「体験の共有」を中心にした文化だからだ。
フェス、ライブ、試合――いずれも現場での参加体験がブランドの核を形成し、ファンはその記憶をSNSで再流通させる。ここに形成されるのは、もはや金銭では測れない「共感経済圏」。それは、消費行動というよりも「感情投資」のネットワークである。