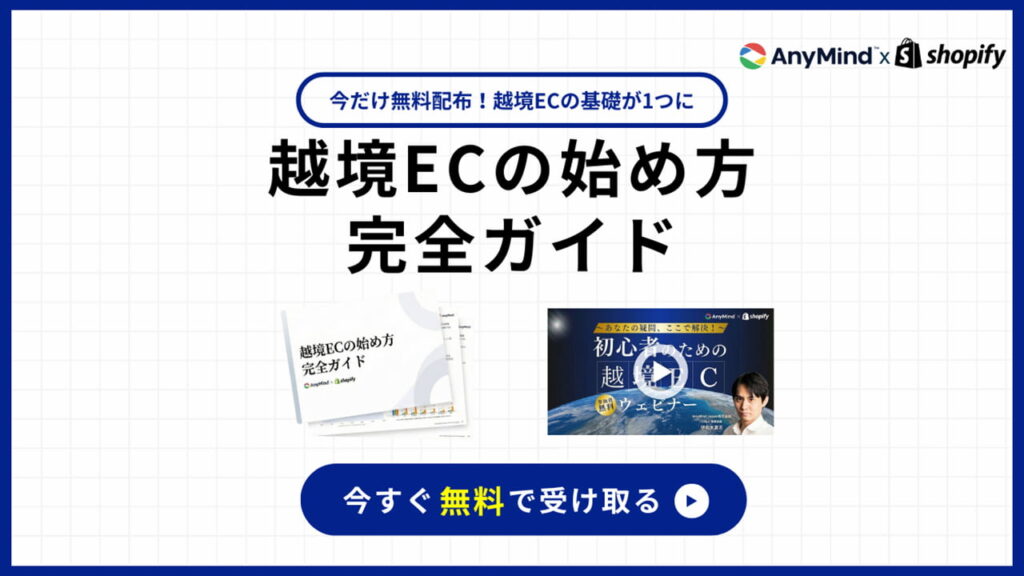今年8月、南海トラフ地震の臨時情報「巨大地震注意」が出された。その後注意の呼びかけは終了したものの、一段階上の「警戒」が出れば社会全体に影響が及ぶことは必至で、対応を再検討している企業も多いはずだ。今回の事態を受けて浮かび上がった広報上のポイントについて、ジャーナリスト・松林薫氏が解説する。
※2024年10月号『広報会議』の連載「記者の行動原理を読む広報術」をダイジェスト版でお届けします。
気象庁は8月8日、宮崎県沖で発生した地震を受けて初めて南海トラフ地震の臨時情報「巨大地震注意」を出した。今回、新たに課題となったのは訪日外国人向けの情報発信ではないだろうか。もちろん、これまでこの問題に注意が払われてこなかったわけではない。しかし、近年の日本文化への関心の高まりや円安の影響に加え、政府がインバウンドを経済政策の柱に据えたことで局面は明らかに変わっている。
筆者は新大阪駅を日常的に利用しているが、新幹線の改札口付近の風景はコロナ禍の収束後、様変わりした。外国人観光客が目立って増えただけでなく、コロナ禍前には目立たなかった欧米系の人たちの比率が高まり多様化しているのだ。夏季休暇のシーズンに入っていることもあり、8月8日もコンコースで列車の遅延に困惑する外国人をたくさん見かけた。
もっとも、JRなど外国語コミュニケーションに慣れている公共機関は、こうした事態でも比較的スムーズに対処している。問題は、人的資源に限りがある地方自治体や民間企業だろう。とくに今回はお盆シーズンと重なったため、十分な対応ができていたとは言い難い。
臨時情報の発表後に観光地も含め訪日客が多い地域をいくつか訪れたが、施設や交通機関が放送や公式サイト、SNSで外国人向けの情報提供を全くしていないケースが少なくなかった。日本語放送ではイベントの中止や行き先の変更に関連して言及していたが、切実に情報を求めているのは大地震についての知識が乏しく慣れてもいない訪日客だろう。
それでもパニックが発生していないのは、Google翻訳やDeepLなど翻訳アプリの普及によって訪日客がある程度の情報を得られるからだと考えられる。外国人が、日本語の張り紙や看板にスマホを向け、「Googleレンズ」などで訳して読んでいる風景はもはやおなじみだ。日本語で情報発信するだけで外国人にも伝わる時代になったのだ。