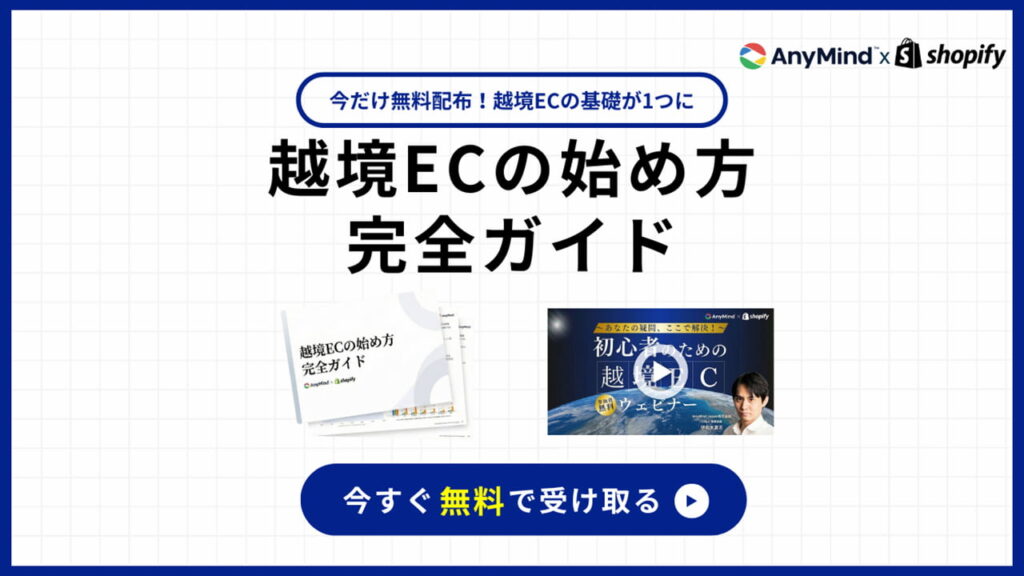※本稿は『広報会議』2024年11月号を転載しています。複雑化する企業の諸問題に、広報はどう立ち向かうべきか、事例をもとに解説する連載「リスク広報最前線」のバックナンバーは、広報会議デジタルマガジンよりご覧ください。
1.危機管理広報は当たり前の時代
この10年での最も大きな変化は、「不正や不祥事を起こした企業は危機管理広報をするのが当たり前」という意識が世の中に定着したことです。
最大の要因は、2016年2月に日本取引所が「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」を策定し「迅速かつ的確な情報開示」を上場会社に求めたことです。
ただし、厳密に言えば、これは上場会社の「開示」を求めただけで、危機管理広報を求めたものではありません。
2.開示や法令に基づく公表とは違う
危機管理広報は、「開示」規制に服していない非上場会社や、法令に基づく公表・報告義務を負っていない状況でも行う必要があります。これは、裁判所も指摘しています。
TOYO TIRE(旧東洋ゴム工業)が大臣認定の性能評価基準に達していない免震ゴムを出荷していたケースで、2024年1月、大阪地裁は、「可及的速やかに国交省に報告するとともに、一般に向けてかかる事実を公表することが求められる」「調査に要するとして長期にわたって報告・公表をしないことは通常は相当ではなく」「調査の途中においても速やかに何らかの報告・公表をすべき場合もある」として、法律上の公表義務がなくても、公表(危機管理広報)が遅れたことについて取締役の法的責任があることを認めました。
しかし、残念ながら、法令に基づく公表・報告義務と危機管理広報とは別ものであることが理解されていないケースも未だに散見されます。
最近では、2024年1月以降の紅麹関連製品での小林製薬の対応です。小林製薬は1月には医師から紅麹関連製品を摂取した消費者に健康危害が生じているとの報告を受けていたものの、消費者庁への報告を必要とする因果関係の有無を明らかにすることに時間を費やし、事実を公表したのは3月22日でした。
報告義務と危機管理広報は別ものであるとの意識があれば、社長が認識した2月6日のタイミングで消費者に向けて注意喚起すべきでした。
3.信頼回復の手段として活用する
危機管理広報を、信頼を回復するための手段として活用している企業も少なくありません。特に大規模な不正・不祥事が起きた場合はなおさらです。