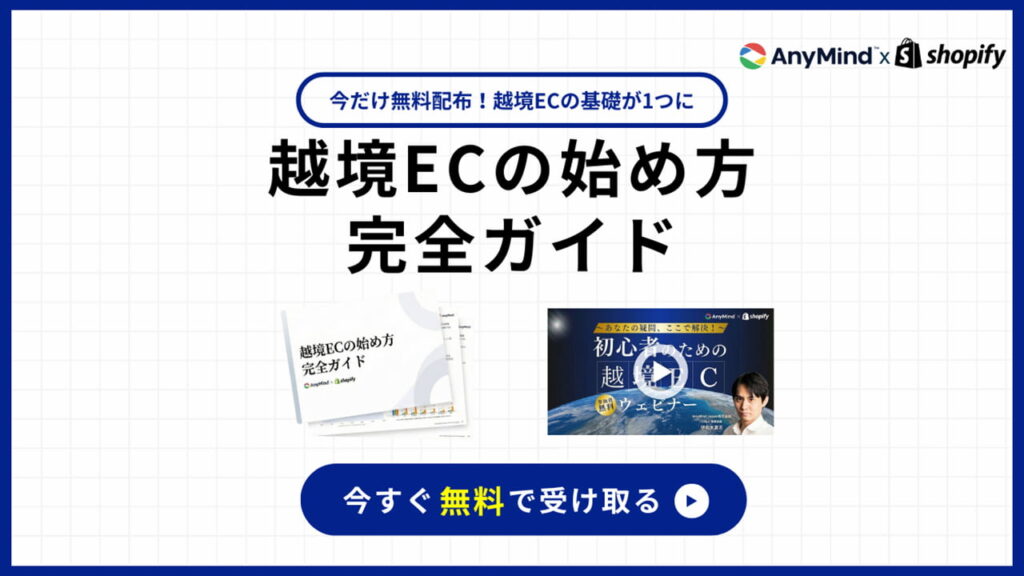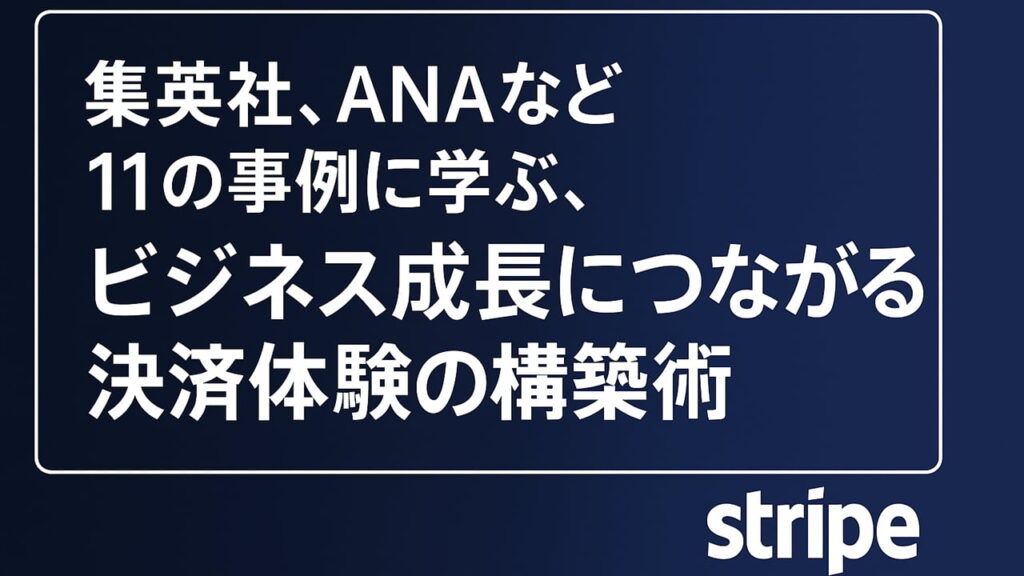【前回】「松尾先生、人工知能と広告の未来はどっちですか?【後編】」はこちら
フィルムへの回帰が起きている
菅付:2010年代の写真はデジタルの浸透によって、2つの領域で大きな変化が起きています。まず1つ目は「写す道具のデジタル化」、そして2つ目は「見せるメディアのデジタル化」です。
写す道具のデジタル化は、なんといってもスマートフォンが象徴的です。iPhoneだけを見ても、半年前の統計では世界で約10億台が売れています。スマートフォンにはカメラが付いており、ほとんどの人が常時、カメラを持って生活しているわけです。
見せるメディアも変化しました。僕らのメインデバイスであるスマホで写真を見せ合う機会も増えています。広告の世界でもデジタルサイネージが普及し、有名なニューヨークのタイムズスクエアも昔はプリント広告が中心でしたが、今はほとんどデジタルサイネージに代わっています。
一方で、こうしたデジタルの普及に対して「フィルムへの回帰」という反動が起きていますよね。
上松:はい、コマーシャル・フォトの読者のプロフォトグラファーに対して「フィルム撮影に興味があるか」と調査をしたところ、20代や30代に「非常に興味がある」「フィルムで撮影してみたい」「実際にフィルムを使っている」という人が多くいました。仕事では圧倒的にデジタルの依頼が多いようですが、特に最近フィルムに興味を持つ人たちが目に付くようになりました。
菅付:ポラロイドフィルムを新たに提供しているインポッシブル社も好調ですし、イギリスの大手ファッションサイト「BoF」でもファッション写真がフィルムに回帰している、という特集記事を出していました。
上松:これまではプロカメラマンの機材は、プロしか扱えませんでした。しかし今は、iPhoneで撮った写真を広告に使えるし、アマチュアでもドローンを飛ばすことができます。一眼レフのカメラで撮影すれば、すぐにモニターで確かめることができるし、手ぶれだって自動的に直してくれるため、失敗がないわけです。そういう中で「プロの存在意義は?プロの技術は何?」と問われています。
菅付:まさに、そういう中で新世代のカメラマンが台頭してきたわけです。この10年間で最も成功したカメラマンの一人であるライアン・マッギンレーにインタビューしたとき、「技術がアートをつくるわけではない。アートは人の心を動かすことだという強いビジョンを持っている。自分にとっての写真は、世界とうまくつながるための言葉である」と話していました。
また、日本の新世代のカメラマンの代表格である奥山由之は「フィルムにはデジタル技術がいくら進歩しても追いつけない何かがある」と言っていました。こうした世代の言動には、デジタルへの反動がかなり大きいのではないかと僕は感じています。
上西:私自身もデジタルに「嫌だな」と感じる部分もあります。シャッターを切る瞬間の緊張感のなさに虚無感やうそくささを感じてしまいます。最近の仕事の8割はフィルムのカメラマンと組んでいます。フィルムでしか撮らないと決めた覚悟に引かれることもありますし、やはりフィルムでしか写らないものに引かれます。
原野:いまの話を聞いて、現代は「ノンフィクション性」が重要になっている、ということかなと思いました。僕はビデオの仕事が多いのですが、OK Goのミュージックビデオ「OK Go: I Won’t Let You Down」もワンショットで撮りましたし、本田技研工業の「Honda. Great Journey.」も、普通はCGを使うシーンを人の手で作った模型を手動で動かして撮りました。
そうすることで、その写真や映像に「これは世界のどこかで人々が集まってつくりあげたのだな」という、そのモーメントを感じさせることができます。インターネットが普及して情報量がとてつもなく多くなってしまったからこそ、「一瞬への価値」や「制作プロセスへの価値」が高まっているのかなと思います。
菅付:原野さんの言う「ノンフィクション性」は、新世代のカメラマンに共通するところだと思います。一瞬にかける緊張感をもう一度、取り戻そうとしているのかもしれません。