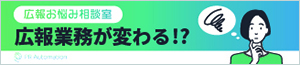元P&G、ステンゲル氏の「目的」別ブランド分類
前回の記事では物語ブランドについて語りました。
今回はその物語にも、いくつかの種類があるということをご紹介したいと思います。これは文学においてはジャンル論と呼ばれる領域です。ブランドの領域における、こうしたジャンル分けの中で、近年もっとも有名なのは元P&Gのジム・ステンゲルの著書『Grow(邦題:本当のブランド理念について語ろう 「志の高さ」を成長に変えたトップ企業50)2011年刊』で語られているブランド理念の分類でしょう。それは下記の5つの理念原則に分類されます。
1.喜びを感じさせる(幸せや驚き、無限の可能性を体験する後押しをする)
2.結びつく事を助ける(他の人達や世界と有意義な形で結びつく能力を高める)
3.探究心を刺激する(新しい世界や経験に乗り出すのを助ける)
4.誇りをかき立てる(自信や力、安心感、活力を高める事を可能にする)
5.社会に影響を及ぼす(現状を揺さぶり、社会全体に好ましい影響を与える)
アップルやグーグルのようなテクノロジー企業は主に「探究心を刺激する」でしょうが、フェイスブックやスターバックスは「結びつく事を助ける」であり、コカ・コーラやマクドナルドは「喜びを感じさせる」ことがその目的と言えるでしょう。
このような分類は、前回紹介したジョナ・サックス氏ほかの論者にとっては、物語に出てくるキャラクターが演じる役割による分類と同じだと言えます。たとえば3のような探究心を刺激する理念とは、冒険者などキャラクターに言い換えられるからです。そしてステンゲルの言う理念とは、そのキャラクターがどういうことに直面するかどうか、つまりはストーリーよりも、彼らが最終的に成し遂げようとする目的に注目したものと言えます。
ステンゲル自身もこれを「Higher Purpose高次元の目的」という言い方をしていますが、ブランドを目的から見直すという視点は、キャラクターの特長のような意味合いでの役割というよりも、もっと大きな意味での物語ブランドの社会的な意味合いを示しているということです。これはブランド論でいえばブランドの使命とも言い換えられるでしょう。
「マーケティング・ジャーニー ~ビジネスの成長のためにマーケターにイノベーションを~」バックナンバー
- 「タイパ」はどのように活用できるか?顧客の体験価値を高める5つのパフォーマンス(2022/11/16)
- 個人について知らなくても集団の動きは予測できる パーコレーション理論がデータ利活用に規制のある時代にマーケターに与えるヒント(2022/4/04)
- なぜ日本企業は累計3000億ドル以上、「スタチン」の売上を得られなかったのか? 「偽の失敗」を見極めてイノベーションを育む(2022/3/01)
- 日本企業からイノベーションが生まれないのは、「失敗が足りない」から?(2022/2/25)
- 「ノイズ」を避けるために、マーケターが持つべき「統計的思考」と「判断の構造化」(2022/2/18)
- マーケターが知るべき人間の判断にまつわる「ノイズ」と「無知」(2022/2/16)
- ヴァージル・アブロー風“デジタルの現実をここに”-CES2022に新たな解釈(2022/2/08)
- なぜ、シニアよりミレニアルが重視されるのか?-メディアと所得の年齢別「格差」(2021/10/06)
新着CM
-
 マーケティング
マーケティング
手作り「スイカバーの素」 ダイソーで先行テスト販売…ロッテ
-
 クリエイティブ
クリエイティブ
サントリー烏龍茶や月桂冠など定番6商品、ファミマカラー限定パッケージに
-
 クリエイティブ
クリエイティブ
ズンズンペンギン、ヌンヌンアザラシ…海の動物が迫るマリンワールドの広告
-
 クリエイティブ
クリエイティブ
新木優子がファッショナブルな間食を提案、湖池屋「ランチパイ」CMの裏側
-
 広報
広報
U-NEXT HOLDINGS、新社名にあわせたブランドコミュニケーション開始
-
AD
 広告ビジネス・メディア
広告ビジネス・メディア
急成長を遂げる「変革支援」のプロ集団 DXとデジタルマーケティングで企業変革を加...
-
 クリエイティブ
クリエイティブ
「一言日記」のような言葉で心を捉えるルミネのコピー、約20年続く理由
-
AD
 特集
特集
成長企業の人材戦略
-
 クリエイティブ
クリエイティブ
お米・人・製品への愛を表現、賀来健人をキャラクターに『亀田の柿の種』の新キャンペ...