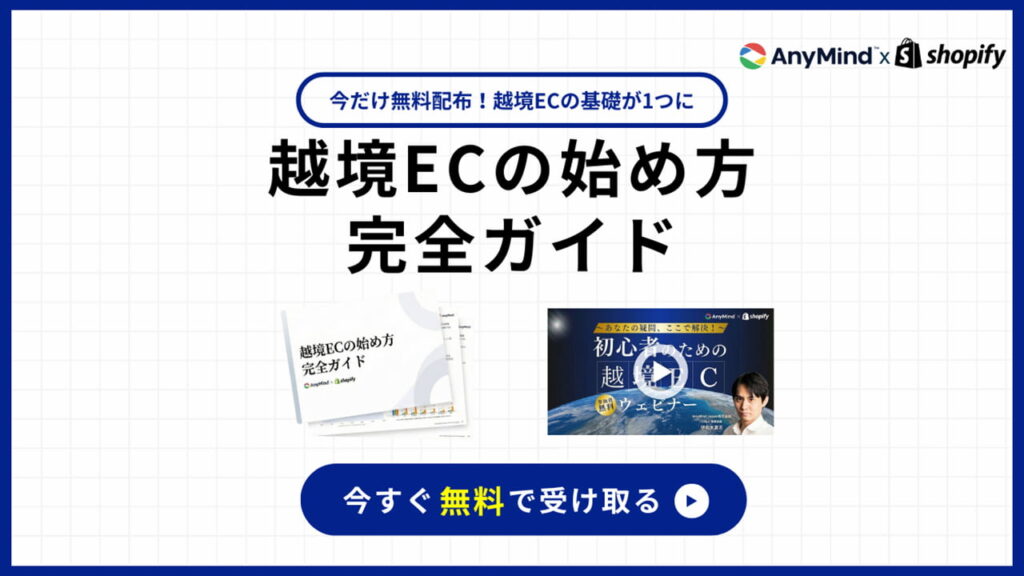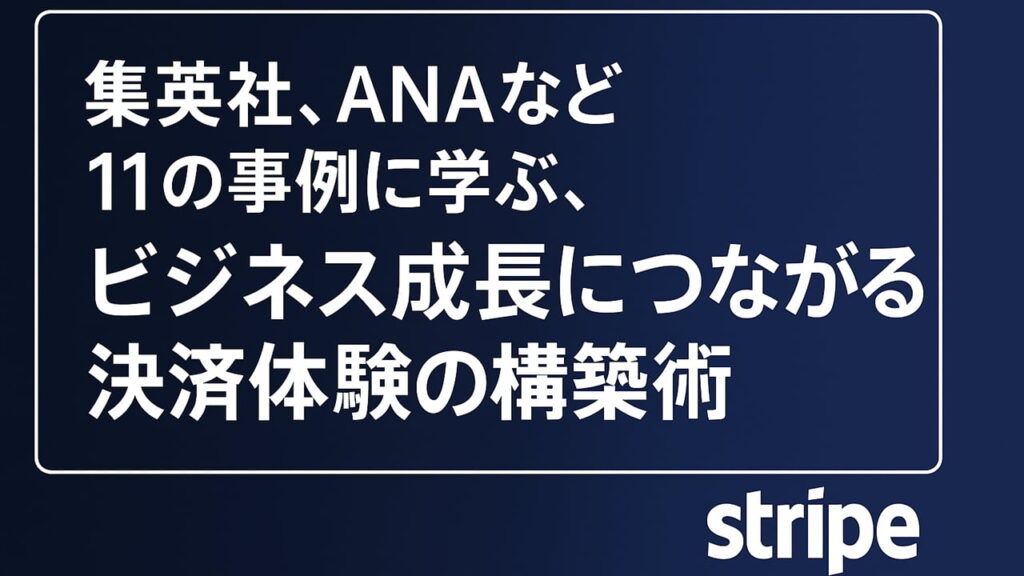「自分のアイデアが本当に受け入れられるだろうか?」「もっと良いアイデアはないだろうか?」…など、常に不安と戦いながら創作活動に勤しむクリエイターにとって、作品が形になるまでの間に編集者との間で行われるコミュニケーションは、時に心の支えになるものです。
クリエイターをモチベートする編集者は、日々形のないゴールの見えない創作活動においてどのようなコミュニケーション、特にフィードバックを行っているのでしょうか。プロフェッショナル編集者の「返信」の極意に迫ります。

ひらりさ氏
1989年東京生まれ。 ライター・編集者。2021年にインタビューエッセイ集『沼で溺れてみたけれど』(講談社)を刊行。オタク女性4人によるサークル「劇団雌猫」メンバーでもある。 代表作に『浪費図鑑』(小学館)、近刊に『世界がひろがる 推し活英語』(学研プラス)など。
―編集とライター、さまざまな立場で仕事をするなか、コミュニケーションで意識してきたことはありますか。
実は、小学生のときから「人の話を聞かない」と言われ続けてきました(笑)。即レスは得意なんですけど、反射で返すと細部を取りこぼしてしまう。例えば、三つのことを聞かれたのに、答えがひとつ抜けていたり、相手が本当に聞きたいことに答えられていなかったり。だからとにかく相手の話をよく聞くこと、メールやメッセージもよく読むことを心がけています。特に仕事の場合は。いつもの100倍くらい注意して聞き役に徹して、相手から何か受け取ることに全神経を集中させます。相手の気持ちを考えるという意味でも、単に聞かれたことに答えればいいのかという意味でも。
―特に編集者という立場ではどうでしょう。
できるだけ相手が返答に迷うポイントがないよう気をつけています。例えば執筆を依頼するとき、原稿料や文字数、形式など、相手が何を求められているのか具体的にイメージできるよう、すべての要素をメールに盛り込みます。相手がやる、やらないをできるだけ判断しやすいように、またあとで言った言わないのトラブルを避けるためにも、言葉でイメージを詰められるものは最初にできるだけ詰めておく。その上で、相手が依頼に対して前向きな姿勢で、企画を掘り下げて進められそうな場合には、打ち合わせなりより負荷の高い仕事をお願いする。これは、AかBかわからなくて時間を使う、といったことで相手の時間を無駄にしないためです。目的も分からず、「とりあえず打ち合わせしましょう」というのが私は嫌なのですが、要するに、わからないものに時間を使いたくないんです。
―言い方やタイミングで意識していることはありますか。
相手から何かボールを受け取ったとき、一番大事なのは、できる限り「受け取りました」と返事をすることだと思っています。ライターの立場で仕事をしていると、出した原稿に対して返事がまったくない人や、何か作業をして1週間くらい経ってメールを返す人もいます。でもそれだと、ボールを投げた側は、次にいつ自分の作業が発生するか分からなくて、スケジュール管理に悩みますよね。すぐ返事が来ると思って作業する時間を空けているかもしれませんし。そもそも、相手の返事を待つ時間というのはストレスであるはず。だからまずはお礼を言うとか、いつまでに戻しますとか、すぐに返すことは大事にしています。