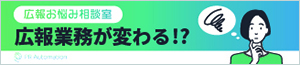平野克己 日本貿易振興機構アジア経済研究所地域研究センター所長

南アフリカ共和国の国旗

南アフリカ共和国第11代大統領のジェイコブ・ズマ(Jacob Gedleyihlekisa Zuma)氏は、COP17が開催されるダーバンのあるクワズール・ナタール州出身。1942年生まれ。小学校5年で中退し、1959年からアフリカ民族会議(ANC)の活動を始め、1990年ナタール州のANC議長に就任した。1997年にANC副議長、1999年にタボ・ムベキ政権で副大統領に就任し、2009年大統領に就任。
11月最終週から南アフリカのダーバンでCOP17(国連気候変動枠組条約第17回締結国会議)が開催された。トヨタの大工場がある、日本人も多く住む街だ。ほんらいは、2012年末失効の京都議定書にかわる新しい合意をつくるための集まり――のはずだった。だが、新合意形成の目途はたっておらず、「ポスト京都」の姿は杳として見えない。
1997年に京都で開かれたCOP3で、日本政府は開催国としての責任をまっとうし、1990年比6%の温暖化ガス排出削減義務を負って京都議定書をまとめた。1970年代の石油危機以降、世界でもっとも効率的な省エネルギー経済を構築してきた日本は、それだけ削減余地が少ない。したがって、国内においてはどの国よりも削減コストがかかる。となれば、「クリーン開発メカニズム」(CDM)を使って開発途上国などで温暖化対策を進め、技術と金を投入して排出権を購入していくしか目標達成の方途がない。そのCDMを確立したのが京都議定書だった。
日本にとってもう一つのアテは原子力だった。日本のエネルギー基本計画は、将来的には原子力発電の比率を50%以上にまで引き上げることを想定している。25%削減の鳩山イニシアティブなどは、原発比率を加速して引き上げなくては達成のしようがないものだった。
しかしながら、CDMの多国間承認がうまく機能していないことから、2012年末までの6%削減は達成不能の情勢である。さらにそこを東日本大震災が襲った。福島第一原発の事故によって既存のエネルギー基本計画は、もはや破綻したのも同然だ。

ダーバンの市庁舎。COP17が開催されるダーバンは、ヨハネスブルグに次ぐ南アフリカ共和国第2の都市。この地域には紀元前10万年頃から狩猟採集を中心とする民族が住んでいたことが知られる。19世紀、イギリスの植民地化とともに近代史が始まった。

ダーバンはインド洋に面した南アフリカ最大の外港都市。人口は450万人(2010年)で、ズールー族が多く、英語よりもズールー語が一般的。インド系移民の人口が約80万人にのぼる。1年を通じてすごしやすい亜熱帯気候であることから、高級リゾート地としての開発が進み、海沿いには大型リゾートホテルが立ち並ぶ。スポーツ施設やインフラが整っていることから、毎年のようにスポーツの世界選手権や、国連の国際会議の開催地として選ばれている。2010年にはFIFAワールドカップの会場の一つになった。
トヨタ自動車の工場があり、自動車の製造が国内首位。

ホウィックの滝。ダーバンのあるクワズール・ナタール州(KwaZulu-Natal Province)にある、ウンジェニ川(Umgeni River)のなかの滝。高さ95メートル。ズールー族は 高いところという意味の「クワノガザ」という名で呼ぶ。地元民のあいだでは、巨大なへびのような生き物が滝つぼの主として住んでおり、信仰の対象としてあがめられていた。今日では人気の高い観光スポットであり、世界遺産の候補にもなっている。
Photo by:Rupert Maspero (www.rmaspero.com)

南アフリカ共和国はアフリカ最大の経済大国であると同時に、自然遺産・生物多様性の宝庫でもある。WW F(世界自然保護基金)の発表によると、今年、南アフリカで密猟の犠牲となったサイの数が341頭にのぼり、昨年の333頭を上回る過去最悪を記録した。ベトナムでは、サイの角はがん治療に効果があると信じられているため、闇取引市場で1本当たり50万ドル(約3900万円)にまで高騰している。ポスト京都の行方は依然として不透明だが、南アフリカ共和国でCOPが開催されることは、新興国における環境保全のあり方を考えるうえで重要な示唆を与えてくれそうだ。
日本のエネルギー政策は見直し必至である。国内で原発を新規に建設することは、とうぶん考えられない。火力発電をリニューアルしながら太陽光発電や風力発電を積極的に推進して、多様な電力をスマートグリッドでむすんでいく新しい社会のあり方が求められている。つまり、省エネ技術の蓄積とクリーンエネルギー開発を結合させたスマートシティ先進国になれるかどうかという課題だ。スマートシティといえば中国の「天津エコシティ」やアラブ首長国連邦の「マスダール・シティ」の建設が始まっているが、日本でも日立製作所が、被災した茨城県日立市においてスマートシティ構想を進めている。しかし、当面のつなぎには火力の増強が要るだろうから、CO2排出量は一時的に増えるかもしれない。
これまで安定した電力供給を誇ってきた日本は、空前の原発事故によって国民生活と産業の根幹をゆさぶられ、現在、エネルギー体制の根本的なつくりなおしができるかどうかを試されているわけだ。その国家的試練に、COP17は大いに関わっているのである。
京都議定書においては、開発途上国は温暖化ガス削減義務を負っていない。米国も参加しなかった。一方、世界最大のCO2排出国は中国で、第二位は米国だ。日本は中国のような国に技術を提供して温暖化対策を支援し排出権を取得していくことになるから、つまりは、京都議定書でもっとも得をするのは中国ということになる。したがって中国は京都議定書の延長継続を主張している。そして、もっとも苦しい立場にあるのが日本だろう。
中国は2009年から対アフリカ政策のなかに気候変動対策支援を加え、アフリカ各国で風力発電や太陽光発電施設の設置、小型水力発電所の建設を精力的に進めてきた。これはおそらく、今度のCOP17をみすえた政策であった。中国と同様、京都議定書の延長を求めているアフリカ諸国の票を、がっちり固めようという思惑だと思われる。
中国は「世界の工場」として世界最大の製造業部門を擁し、多大な資源とエネルギーを消費しながら先進国に製品を供給している。そのような中国の立場からすれば、先進国が国内生産を途上国に移転してCO2排出量を減らすことに反発があっておかしくない。中国は、先進諸国に対して削減目標のかさ上げを要求してきた。その中国がアフリカ票を取り込むことに成功すれば、日本はますます不利な立場に追い込まれてしまう。
一方日本はカナダやロシアとともに、米中が削減義務を負わないかたちでの京都議定書の延長には反対している。日本政府のカウンターオファーは、多国間枠組みであるCDMにかわって、各途上国と二国間で排出権を取引できる制度を導入することである。省エネ先進国の日本にとっては、ほかの先進国と同等の削減義務を課せられると不利になる。それよりも、資源効率の悪い国に日本の技術を広く普及させて世界全体の気候変動対策に貢献するという道筋を確立できれば、それがもっとも望ましい。そのほうがおそらく、世界全体で計った費用対効果も高くなるだろう。
電力不足にあえぐアフリカ 日本の活路は技術支援にあり
日本としては、アフリカ諸国に対するバイの気候変動対策支援をコミットすることで、COP17議長国である南アフリカをはじめアフリカ各国の賛同をえたいところだ。しかし、アフリカにおける日本の外交力は中国に遠く及ばない。2009年から手をうってきた中国に比べると、出足も遅かった。
しかしその一方で、資源高のなかで急速な経済成長を続けているアフリカは電力不足に苦しんでいる。そこにビジネスチャンスをみいだした日本企業はアフリカ展開をはかっており、先述の日立も先陣をきった企業のひとつだ。気候変動対策に関する日本政府のアフリカ支援も始まった。COP17開催国の南アフリカにはアフリカ最強の電力公社エスコムがある。赤道以南アフリカの電源の80%はエスコムのものだ。エスコムが中心となって、赤道以南アフリカは超広域の送電網でむすばれている。この電力網のなかには、日本が必要とする資源をもった国も多数含まれている。
九電力会社体制と原発推進政策のなかで、日本国内ではながらく逼塞してきた新エネルギー技術の開発現場が、広大なアフリカ大陸に拓けようとしている。日本がこれから必要としている技術を、アフリカとともに開拓していく地平が広がっているのだ。日本経済の再生と国土復興という喫緊の課題。それとアフリカ開発支援や気候変動対策が、このようにして連動しようとしている。
エネルギー問題や自然環境保護など、環境問題への対策や社会貢献活動は、いまや広告・広報、ステークホルダー・コミュニケーションに欠かせないものとなっています。そこで、宣伝会議では、社会環境や地球環境など、外部との関わり方を考える『環境会議』と組織の啓蒙や、人の生き方など、内部と向き合う『人間会議』を両輪に、企業のCSRコミュニケーションに欠かせない情報をお届けします。 発行:年4回(3月、6月、9月、12月の5日発売)
新着CM
-
 販売促進
販売促進
ファンタジー好きに訴求するグミ カンロ、空想の果実をイメージした新商品
-
AD
 宣伝会議
宣伝会議
【広報部対象】旭化成のグローバル社内イベント成功事例を紹介
-
 販売促進
販売促進
横須賀市、メタバースで観光誘致 AIアバターの実証も開始
-
AD
 マーケティング
マーケティング
企業のパーパスに共感してもらうことが、デジタルコミュニケーションの近道に
-
 コラム
コラム
サムライマックのCMに「ありがとう」と言いたい(遠山大輔)【前編】
-
 クリエイティブ (コラム)
クリエイティブ (コラム)
アイデアが苦し紛れにくっつく瞬間がある――「KINCHO」ラジオCM制作の裏側
-
 販売促進
販売促進
ベビー用品の速達デリバリー 日本トイザらス、30分以内におむつやミルクを配達
-
 販売促進
販売促進
「認知獲得」「販促」の両方使えるリテールメディア特性がメーカーの混乱を招く
-
 特集
特集
「宣伝会議賞」特集