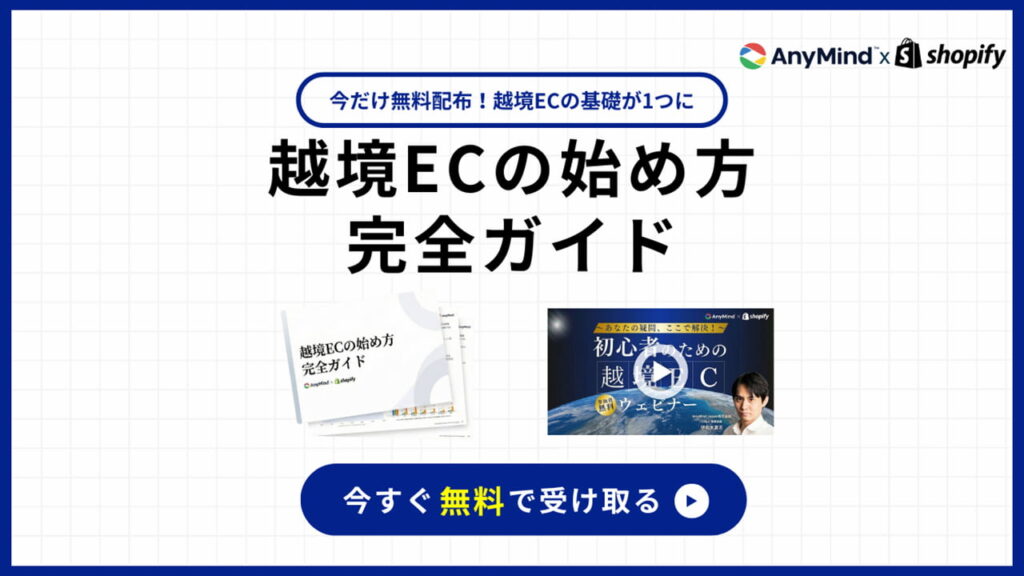さて、3回にわたって、あらゆるコンテンツ形態をマッピングする3つの軸について解説してきました。今回はその最終回、「リニア」⇔「ノンリニア」の軸について解説します。この「リニア」⇔「ノンリニア」なメディア特性の違いこそ、現代のスマホ&ソーシャル浸透の波が、コンテンツ消費のあり方を変え、いわゆる「マイクロ・コンテンツ化」が進む中で、是非とも理解すべき観点だと私は思います。
まず、「リニア」なコンテンツとは何か? から説明しましょう。リニアとは線形のことです。メディア・コンテンツの消費に即して言えば、リニアなコンテンツとは、初めから終わりまで一直線に連続した形で見てもらえることを想定したコンテンツのことになります。
筆者が思う、最も「リニア」なコンテンツ形態が映画です。映画は、これ以上は考えられない!というくらいに「リニア」に振り切ったコンテンツの形態です。この映画が持つリニア性、さらには「特権」について把握することが、「リニア」なコンテンツとは何かを理解するうえで、良い補助線になると思いますので、これから、しばらく映画に基づいて、解説していきます。(映画以外には、長編小説がリニアなコンテンツの代表例と思いますが映画に比べればリニア性は随分と薄まります)
皆さん、映画監督という職種についてどう思いますか? 世の中には様々なクリエティブ職業が数々ありますが、映画監督は、最も尊敬され、憧れられるクリエイター職の一つですよね。
こういうことをアドタイで書くのも挑発的ですが、ワイドショウ的な文脈でいう世間では、映画監督のほうが、CMディレクターよりも、「ありがたい存在」「偉い存在」と思われていそうなことは間違いありません。「巨匠」とか枕詞が付いている映像クリエイターは大体が映画監督ですよね?
これは何故でしょうか?
アウトプットがどれだけ沢山の人の目に触れるか? という観点で言えば、CMディレクターのほうが、そこらへんの映画監督よりも、よほど沢山の人に見られ、影響を与え得るものを作っています。また、予算的な面で見ても、もちろんハリウッド的な大作映画は予算の絶対額は巨額ですが、例えば、日本国内で発注される案件において、1秒あたりの制作費という観点で比較するならば、今ではCM映像のほうが、映画やテレビドラマよりも、よほど潤沢に予算を投じて作っているケースも多いように思います。
では、映画監督だけが、CMディレクターや、テレビドラマのディレクターにもないある種のリスペクトを社会から享受している理由は何でしょうか? さらには、映像というジャンルすら超えて、雑誌の編集長や報道ジャーナリスト以上の属人的尊敬と名声を獲得しうる理由は何故でしょうか?
筆者が考える、その最大の理由の一つは、映画監督は、現代のメディア・コンテンツ制作者の中では、他の職種では想像すらできないくらい、時間軸のコントロール権を留保している職種だからではないか、と思っています。
実際に映画というコンテンツが消費される最前線である「映画館」で映画を見るというシチュエーションをイメージしてもらえば、納得いただけると思います。ひとたび、お客を、映画館の中に連れてきてしまえば、2時間もの長時間に渡って「オレ様ワールド」を存分に展開することが可能です。鑑賞者は、どういう映像を、どういう順序で、どのように見せられるか? その時間軸について、全権を映画作家に預け、ある意味では、物理的にも、その身を委ねざるを得ないのです。もちろん、途中で映画館を退席する自由というものはあるのですが、よほど気分が悪くなったりするなどの体調不良でもない限り、ほとんどの人はこの権利を使いません。あとは、お客の立場としてできることは、寝ることくらいですね。
以前のコラムで、アナログ盤からCDへと音楽流通の形態が変化をすることで、ポップミュージックの作曲者は、サビ頭の曲構成にすることを強いられ、曲構成の自由を意図せずして失ってしまったという話をしました。しかし、映画では、未だに、「ツカミ」のために、ハイライトの場面をいきなり、冒頭に持ってきたりしませんよね。推理サスペンスもので言えば、種明かしを冒頭に持ってくるなどありえません。映画の作り手である監督は、CMディレクターやテレビドラマのディレクターのように、「退屈だと飛ばし見されるのでないか?チャンネルを変えられるのでないか?」というような心配をせずに、約2時間もの時間軸を使うことができます。そのお陰でじっくりと、伏線を張り巡らし、観客の脳内において、描きたいイメージやストーリーを、あたかもレンガを積んで、建築物を作るようにじっくりと積み上げ、全ての伏線が一点に集中するような形で、ドラマとしてのクライマックスを盛り上げることが出来るのです。
ビョークが主演し、2000年度カンヌ映画祭でパルムドールを受賞した「ダンサー・イン・ザ・ダーク」という映画があります。筆者はこの映画を、劇場で見た際に、その映像が、酷く手ブレしたカメラで撮影されているために、映画を見ているうちに酔ってしまい、気分が悪くなり、しまいには吐き気すら催しすらました。ご覧を頂いた方は分かると思いますが、何とも救いのない沈痛なストーリーの映画です。はっきりいって鑑賞後の感想としては、ある面では「極めて不愉快」とすら言える映画でありました。吐き気を抑え、何とか見終え、ほうぼうのていで、劇場のロビーに這い出て、帰り道では、腹が立つのを通り越し、あの監督は、何故あんなに手ブレした映像を用いたのだろうか? なんで、お金を払ってきた観客を、こんなに不愉快な目に合わせるのか? と監督の意図に興味が湧いて来ました。あれこれと想像するうちに、あの手ブレ映像は、主人公セルマが味わっていた世界を生きることへの「苦痛」というものを、観客にも味わい、共有してほしい、という監督の意図がこもった演出技法なのでないか、とハっと思い当たりました。そして、もし、これが劇場でなく、例えばテレビでの放送だったら、途中で迷わずにチャンネルを変えただろうし、DVDならば、スキップするか、途中で見るのを止めていたに違いない、この「不愉快さ」は劇場で映画を見るというコンテンツ消費だからこそ起こり得た経験あるいは、映画だからこそ残し得た自分という観客の心の中への「傷あと」なのだ、と気づきました。筆者は、その時、映画自体の内容についての出来の良し悪しを脇において、「映画」というコンテンツのあり方そのものがやはり凄いのだ。メディア芸術の最高峰と言われるだけのことはある、と痛感しました(上記は、単に監督の意図を私が深読みしたのかもしれませんが)。
(次ページヘ続く)