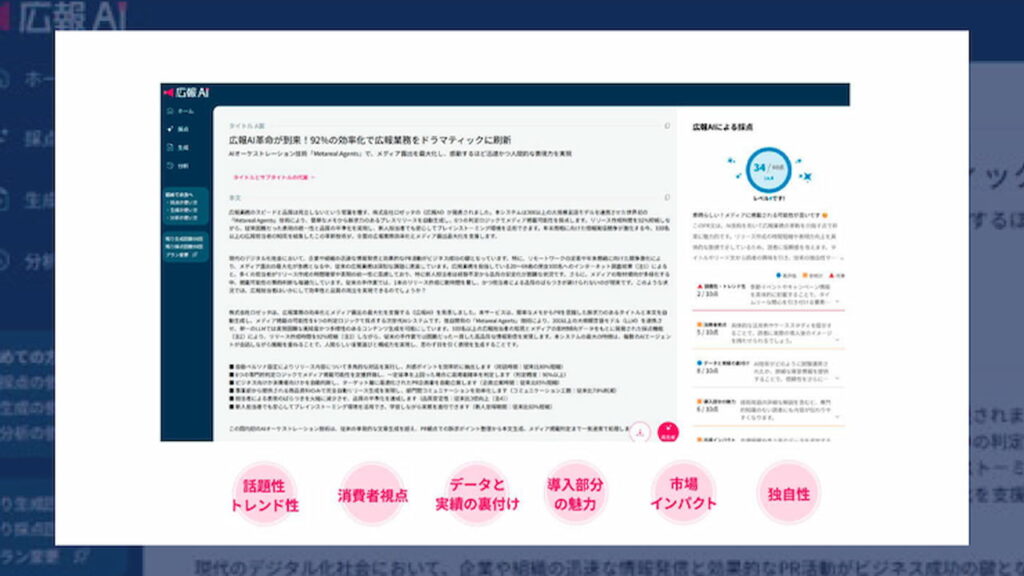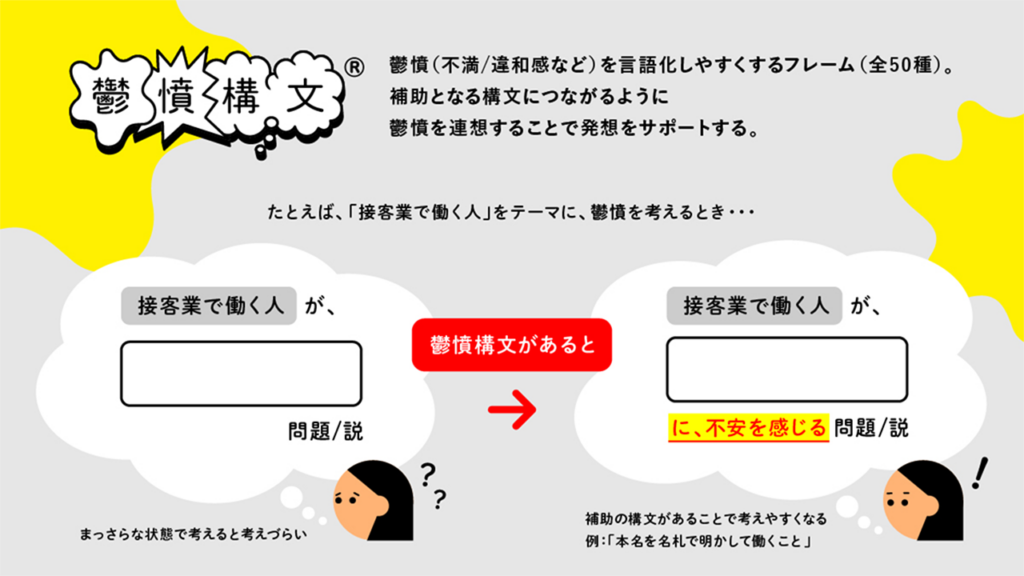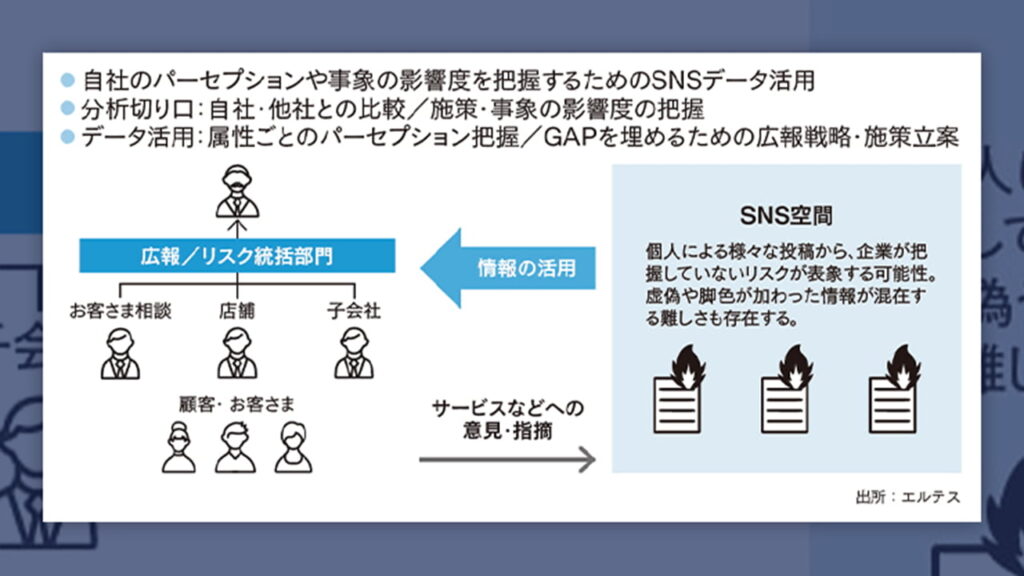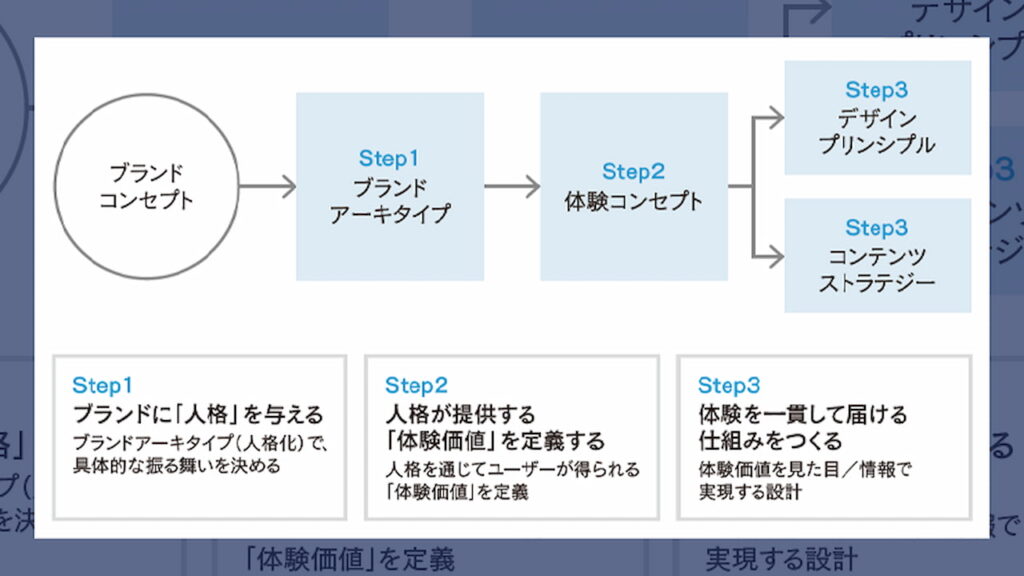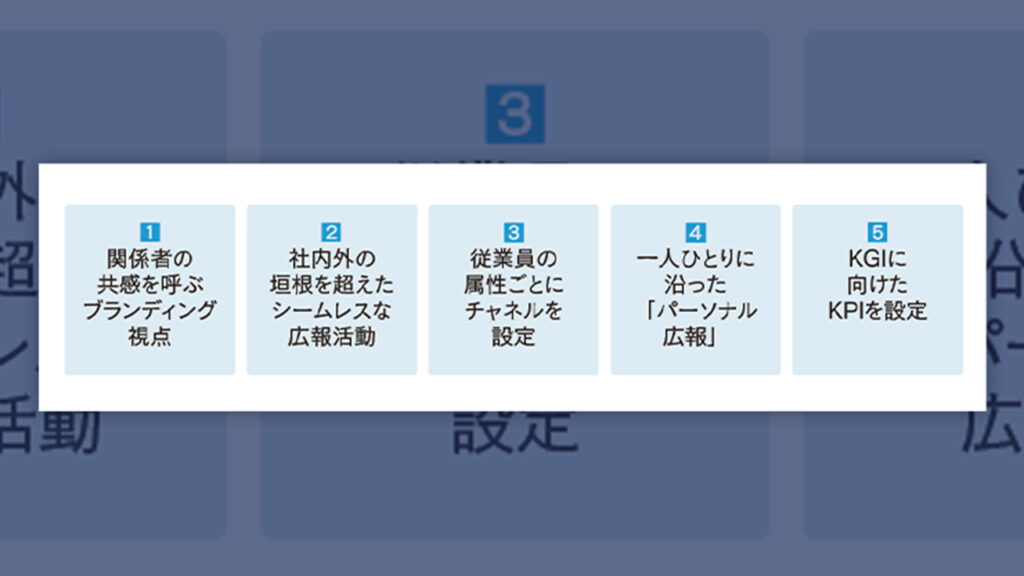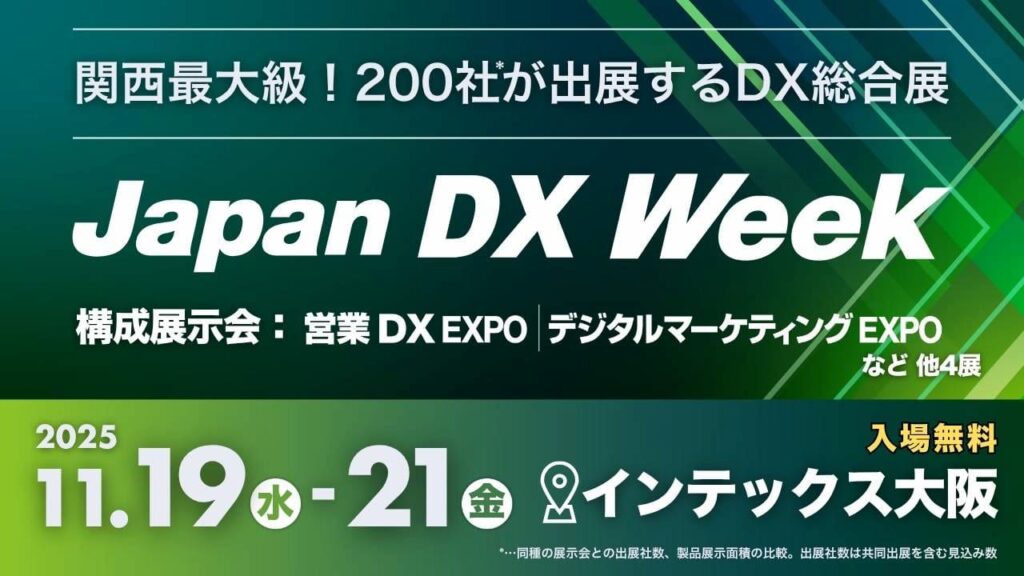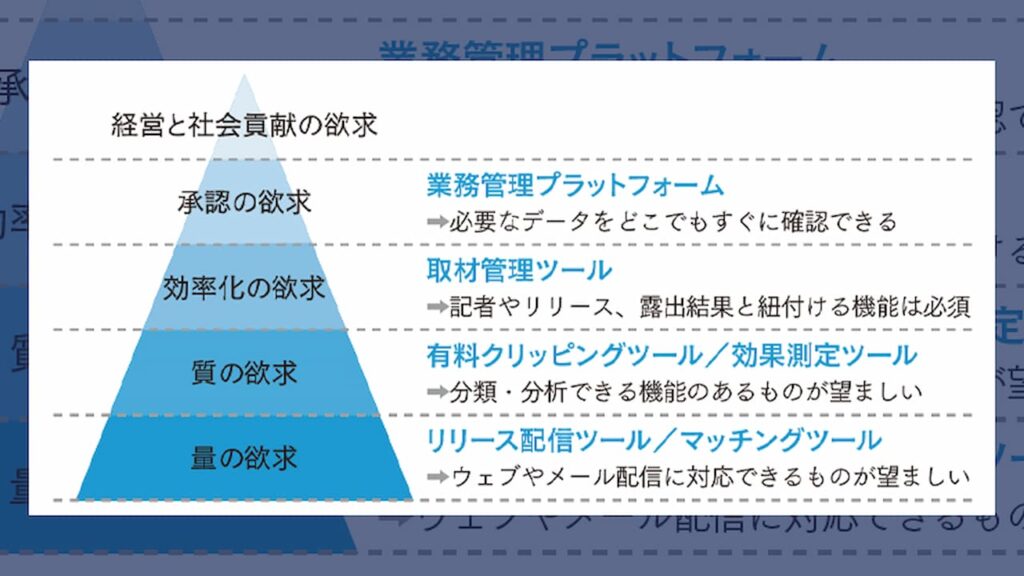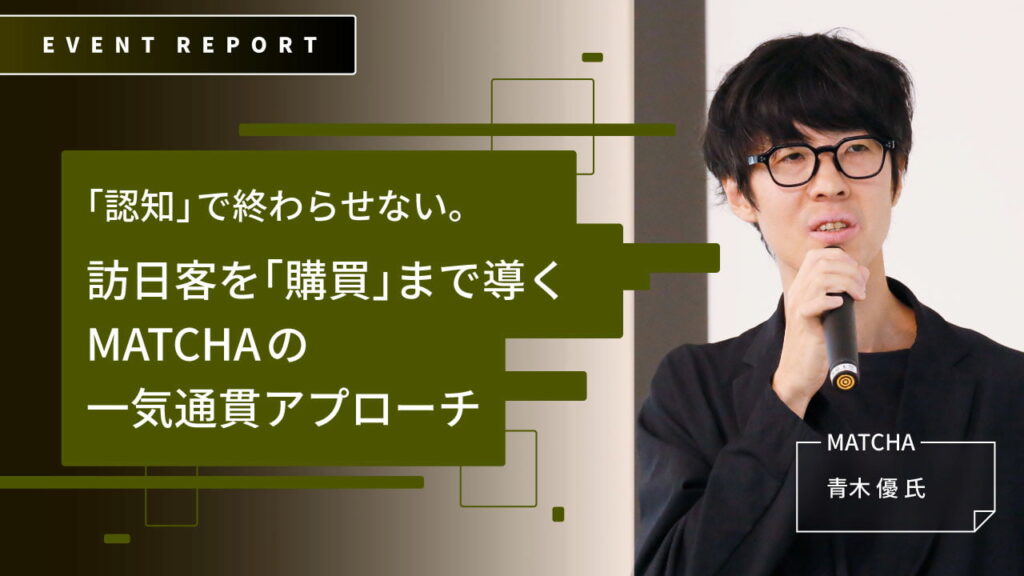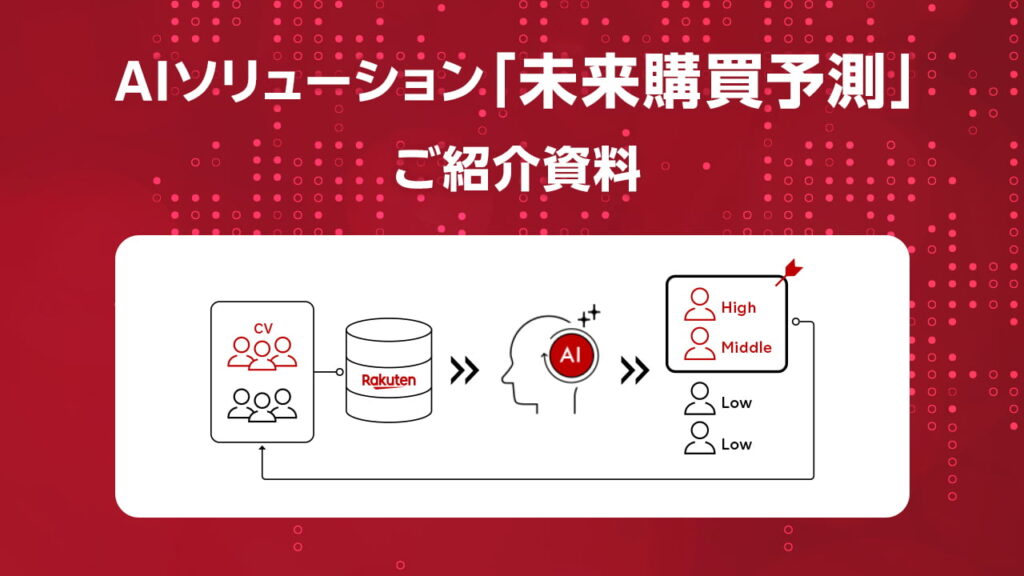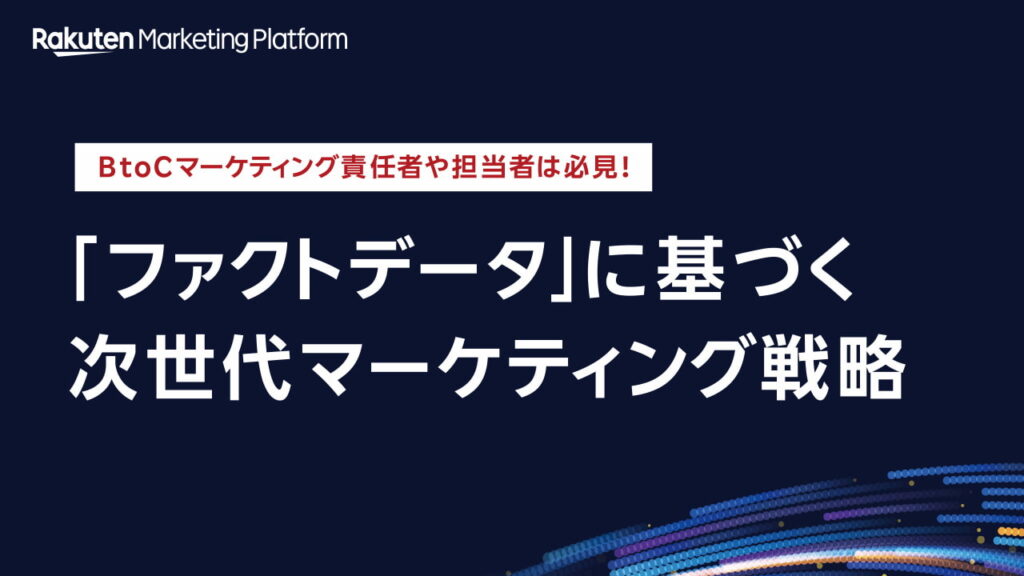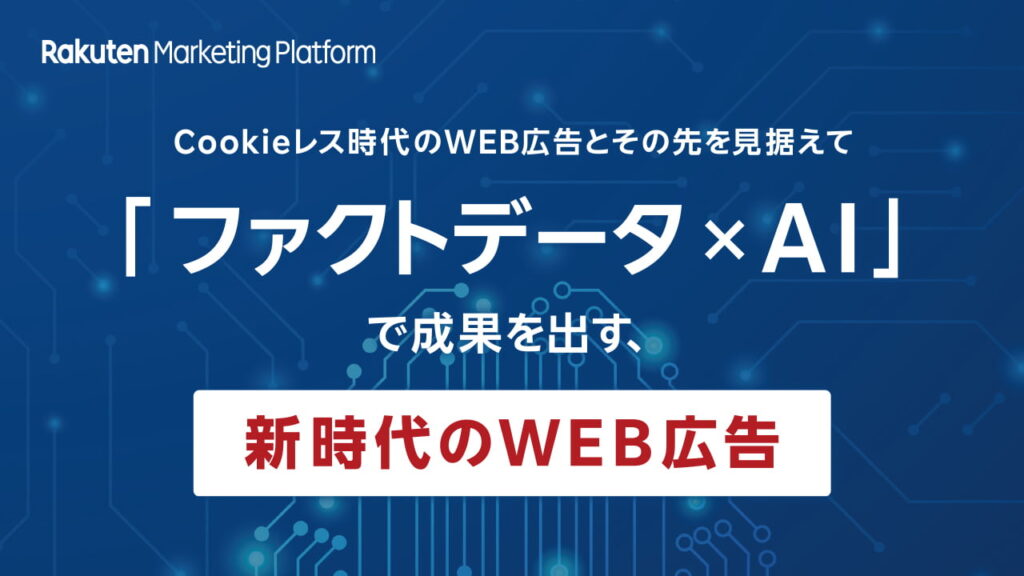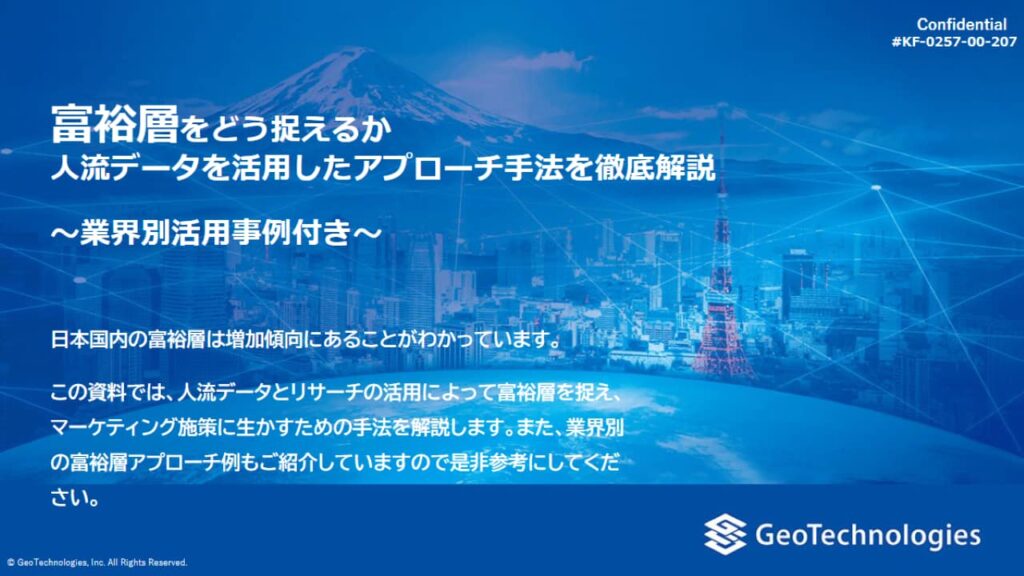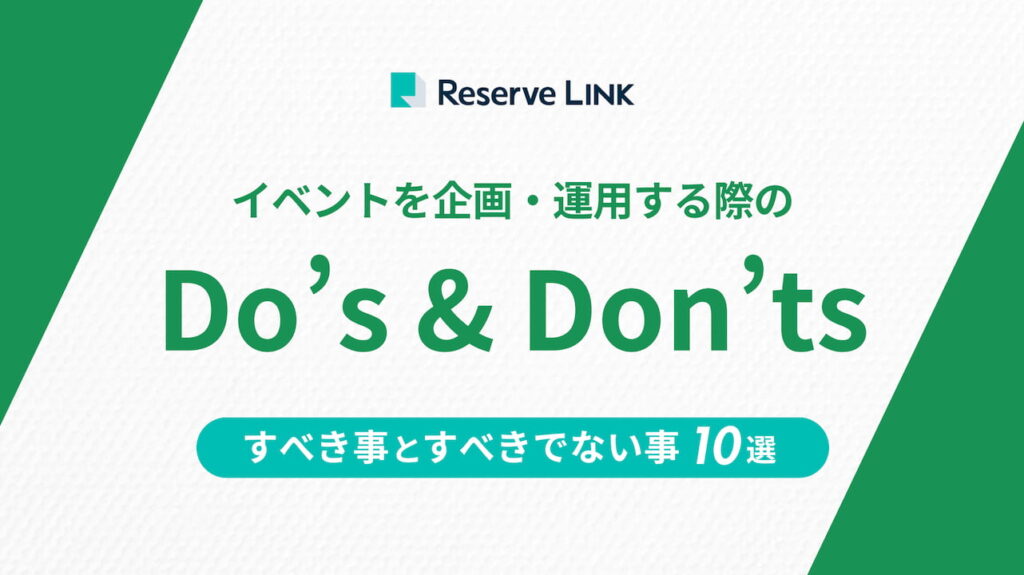本稿では「エンゲージメント」という指標を、とらえ直してみたい。
最近になってメディア、そして広告の分野で多用されるようになった、この概念は「オーディエンス(ユーザー)・エンゲージメント」などとも呼ばれ、読者(ユーザー)にとってどれほど親しく、良好な関係にあるかを表す指標として期待が高まっている。
注目度の高まりを受けて、編集者や記者とは別に、オーディエンス・エンゲージメント担当を置くメディア企業の事例も増えている。しかし、“エンゲージメント万能”となっては、副作用も生じかねないというのが筆者の視点だ。
本稿はメディアの価値を追求するに際して、エンゲージメントの意義を確認すると同時に、その課題についても取り扱いたい。
さて、改めてエンゲージメントとは何だろう?
本連載「
メディアはどうすれば「PV」や「UU」といった「規模的」指標から脱することができるのか
」で、概略的に触れている。
エンゲージメントとは、端的にいえば“(ユーザーからの)関係性を示す指標”と理解できる。むろん、品質的アプローチも、良好な関係性(たとえば、「信頼」)を築くひとつの要因だろう。
定まらない、その“定義”
当然ながら、読者との良好な関係が高まっていくことがメディアにとって大切なのは当然だ。では、それを計量的に確認できる指標があるのかといえば、多くのメディア運営者は困惑しているのも現実のようだ。
米国で広く使われるメディア分析サービスの「PARSE.LY」は、数千に及ぶメディア運営者に「オーディエンス・エンゲージメントの定義を定めているか?」「それを重視しているか?」「それはどんな指標から得られるか?」などを尋ねる調査を2016年に実施した。
KAIGI IDにログインすると、すべての記事が無料で読み放題となります。
「AdverTimes. (アドタイ)」の記事はすべて無料です
会員登録により、興味に合った記事や情報をお届けします
藤村 厚夫(スマートニュース)
90年代を、アスキー(当時)で書籍および雑誌編集者、および日本アイ・ビー・エムでコラボレーションソフトウェアのマーケティング責任者として過ごす。
2000年に技術者向けオンラインメディア「@IT」を立ち上げるべく、アットマーク・アイティを創業。2005年に合併を通じてアイティメディアの代表取締役会長として、2000年代をデジタルメディアの経営者として過ごす。
2011年に同社退任以後は、モバイルテクノロジーを軸とするデジタルメディア基盤技術と新たなメディアビジネスのあり方を模索中。2013年より現職にて「SmartNews(スマートニュース)」のメディア事業開発を担当。
90年代を、アスキー(当時)で書籍および雑誌編集者、および日本アイ・ビー・エムでコラボレーションソフトウェアのマーケティング責任者として過ごす。
2000年に技術者向けオンラインメディア「@IT」を立ち上げるべく、アットマーク・アイティを創業。2005年に合併を通じてアイティメディアの代表取締役会長として、2000年代をデジタルメディアの経営者として過ごす。
2011年に同社退任以後は、モバイルテクノロジーを軸とするデジタルメディア基盤技術と新たなメディアビジネスのあり方を模索中。2013年より現職にて「SmartNews(スマートニュース)」のメディア事業開発を担当。
この記事の感想を
教えて下さい。
この記事の感想を教えて下さい。